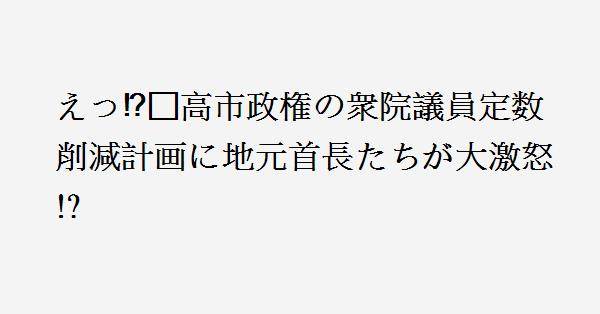
高市政権の元で、自民党と日本維新の会が衆院議員定数削減を議論していますが、地方の首長や政党からは反発が相次いでいます。九州市長会長の大西一史・熊本市長や沖縄県の玉城デニー知事は、多様な国民の声を反映する重要性を強調し、削減に慎重な議論を求めています。特に比例選の議席削減が取り沙汰されており、これにより少数政党の声が届かなくなることを懸念する声があります。
公明党や共産党の幹部も削減に反対し、「政治とカネ」の問題を引っ込めるための手段ではないかと指摘。自民党内からも、定数削減の是非について与野党で丁寧な議論を求める声が上がっています。一方で、一部の有権者は財源確保や物価高対策のために削減を支持しています。

議員定数削減の議論は、一見して国の支出削減や効率化を目指すものであり得るが、その裏には地方や少数派の声を軽んじるリスクが潜んでいる。地方の首長たちの反発は、まさにこの点に集約される。現状では、多様な意見を国会に届けるための重要な仕組みである比例代表制が、削減のターゲットとなっている。制度の欠陥は、選挙の公平性を確保するために必要な「死に票」の拾い上げを軽視する点にあり、同時に少数意見を切り捨てる結果を招く可能性を孕む。本質的な問題解決には、第一に、有権者の多様な意見を尊重する選挙制度改正の議論を深化させる必要がある。
第二に、地方の実情を考慮した均衡の取れた定数調整が求められ、さらには政治とカネの透明性を高める制度改革が必須である。この変革を進めることにより、効率と公正を両立した政治体制が実現する。議論の焦点を「削減そのもの」ではなく、「国民の声をどう反映するか」に移行させることこそが、未来の日本の民主主義にとって重要なのだ。議員定数は単なる数字ではなく、民主主義の質を問う指標であると認識する姿勢が求められる。
ネットからのコメント
1、実際国会で少数の声の側である人達がどういった貢献をされてきたのか検証してみてもいいんじゃないでしょうか。国民から小選挙区でNOを言われて比例で上がってくる人間達がどんな人達だったのか。よくよく検証してみて欲しいと思います。個人的には国会に必要が無いと感じる事の方が多いです。
2、たとえ議員の数が「増えた」としても、少数の声は拾われない。なぜなら、議員側の資質・行動にも問題である事が多いから。「これだけ議員がいても少数の声が反映されてない」と考えの視点を変えるべきだと思います。少数の声を拾うにしても、現代でインターネットが普及している。
発信者自体は増えている時代です。ネット社会や現場での声に対応して意見を汲み上げている議員はどれだけいるでしょう。(地方議員も国会議員も、パソコンすら使えない議員が多くいる。以前もデジタル大臣が使えない例もありましたよね)議員側の議会での言動の精査もすべきだし行うべきでしょう。多くの議員は自分たちのしたい事・都合の良い事の為に意見を述べてる方が多いと思います。自分たちの行動を省みた上で、「減らすのは、、」と言う意見を言うべきですね。
3、衆議院の選挙制度が小選挙区へ改正された大きな目的の一つが2大政党の切磋琢磨。大きな国民的課題を、異なった政治勢力が民意を汲みながら実現していくことが可能になると、2大勢力による政治選択を選ぶのがその時々の民意を組むのに適しているとされたからである。当あるいは2大政党の候補者が負けたにもかかわらず、比例復活する事が如実に現れ、近年は小勢力乱立による政治的不安定が増してきている。比例区の必要性を認めるけれど、現在の定数465人のうち約38%の176人が比例区代表と、その割合が少し多いように思う。
ここから50人を削減すると、約30%となって、その弊害が小さくなるy。小政党にも一定の配慮が出来ている。より良い制度設計と、議員削減を実現する比例区減による議員定数柵威厳は理にかなっているでしょう。
4、高市氏と維新の間で衆議院数の1割を削減する旨が合意となったが、確かに議員数が減れば歳費、つまり支出も減るが、無論本質はそこではなく、議員として使命感を持って働いている者を削減する必要はなく、ここでモチベーションの低い議員や働かない議員を選別し、削減できるのならば理想的だと思います。そのような議員が少なくとも1割くらいは居そうな思いがします。地方の声が届きにくくなるとの反対意見もありますが、働きの良くない議員ならば、居てもいなくても同じだと思います。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/1facf15458d8172502696290916144e020ce31ba,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















