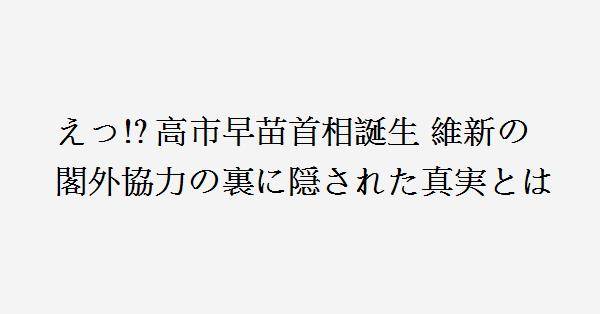
10月21日、自民党総裁の高市早苗氏が憲政史上初の女性首相に選出された。高市氏の就任までの過程は困難を極めた。当初、公明党が連立から離脱し、自公政権は少数与党状態だった。しかし、日本維新の会の協力により自民党196議席、維新35議席で計231議席となり、無所属議員の支持も得て衆院過半数を達成した。維新は閣外協力を選択し、大臣ポストにこだわらず政策実現を目指す方針を示したが、内部には大臣ポストを求める声がある。
また、選挙区調整に対する懸念も存在し、維新の内部では次の選挙への不安が広がっている。

この状況は、現代政治における奇妙な連立の現状を象徴している。維新は自民と連立することで政策実現を目指しているが、その過程で失われる可能性のある独立性を考慮すると、連立が維新にとって本当に利益となるのかが疑問である。問題の本質は、連立政治の不安定さと政治の効率性にある。維新が閣内に入らなかったことは、政策実現の手段を失う可能性が高く、閣内に入ることは政策決定に直接関与する重要な位置を確保するための手段だ。解決策として、維新は議席数を増やすことで交渉の力を高める、または自民党と明確な政策協定を結ぶことでその影響力を強める必要がある。そして、選挙区調整の際の明確な条件を設定し、議員の不安を解消することが求められる。
政治は国民の利益を守るための手段であるべきであり、連立の過程が国民に混乱をもたらすことがあってはならない。政策実現を目指すならば、その手段は安定的で透明であるべきだ。
ネットからのコメント
1、高市首相の誕生は歴史的な一歩だけど、自民・維新の連立にはまだ課題が多そうですね。維新内部で「大臣ポストを取るべき」という声が出るのも当然だと思います。政策を実現するには責任ある立場が必要だし、選挙区調整の不安も現実的。ただ、国民としては、ポスト争いよりも、生活に直結する政策がしっかり進むことを願っています。連立の形にこだわるより、結果で信頼を得てほしいです。
2、自公のように選挙区調整、選挙協力をガッチリやってる国は例外中の例外。それが可能なら、そもそも別々の党でいる必要がないから。他党連立が当たり前の欧州では、政権運営と選挙は別と割り切っているので、選挙で確定した議席数に応じて随時連立を組み換えるのが普通。日本も今回の自維との関係がそれに近い物となり、今後の連立の雛型になると思う。
3、馬場氏の入閣は100歩譲って有りだとしても前原氏の入閣はいくらなんでもやめた方が良いでしょうね。
それにほとんどが当選2~3期未満の議員ばかりで大臣職務めるにはちょっと無理があると思うから、政務官ポストとかを経験すべき。あと「選挙区調整が怖い」というのは比例復活でしか受かる道筋が無いという事を自ら言ってる訳でそんな人別に要らんと思う。党として本当に必要な人材なら比例名簿順位上位に入れてもらえるでしょ。そもそも衆院で言えば大阪全てと兵庫の1つで小選挙区当選して、残りは全部比例復活っていびつな党なんやから。
4、吉村代表はあれだけ強烈に覚悟、本気を表していたのに結局維新は高市政権に閣外協力するだけになった。それなのに何故連立という言葉を使い続けるのか?維新の党内ガバナンスは脇が甘すぎることで有名。そういう組織でトップが乱暴なことをするから内部で不協和音が出て当然。自民からすれば連立で維新を抱え込まなくて正解という見方もある。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/e875f12aece2da08fc9a6f1856100f743d666389,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















