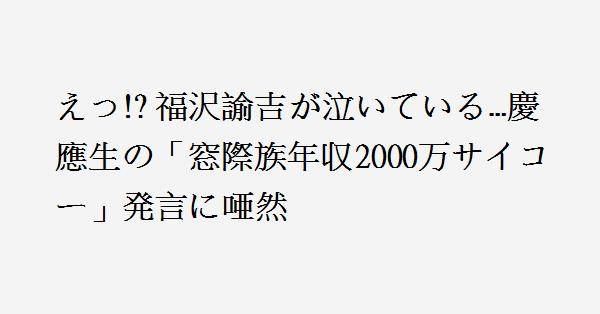
日本の教育問題を分析する中で、福沢諭吉の教育理念の劣化が焦点となっています。慶應義塾大学の学生が「年収2000万円の窓際族」を肯定する発言は、日本の大学がかつて目指していた自主自尊の精神から離れ、単なる生存を目的とした機関に変わりつつあることを示唆します。教育思想家の高部大問は、大学が国からの補助金に依存し、経営主体が変質していると指摘します。
これが学生に与える影響はおおきく、受験地獄や非人間的な入試制度が子どもたちの夢を奪う要因となり、創立者の理念から遠ざかる現状が続いています。

現状は異常と言わざるを得ません。国からの補助金依存が習慣化し、学生や大学関係者が建学の精神を見失っている状態では、本来の教育の目的を果たせません。大学は次世代の人材育成機関であり、個性を尊重する場であるべきなのに、制度がそれを阻んでいるのは問題です。一つ目の解決策として、補助金の使途を透明化し、大学の独立性を強化することが必要です。次に、教育基本法に基づき入試制度を抜本的に改革し、多様な評価基準を導入するべきです。最後に、大学教育の理念を深く理解させるための教師育成プログラムを充実させることが不可欠です。大学とは人格形成の舞台であり、ただ生き延びるための手段ではありません。
我々が目指すべきは、ただ知識を詰め込む教育ではなく、思想や文化を育む場であるという価値観を取り戻すことです。
ネットからのコメント
1、ペーパー試験は、勉強ばかり、暗記偏重で思考力のない子供を育てる!という批判から推薦入試や総合型(AO)を増やした結果、勉強すらろくにせず、遊んでたやつらが続々と大学に潜り込み、さらに遊び呆けるという悪循環になりました。指定校であれば体育などを含めた全科目の成績や部活動の取り組みを、総合型であれば部活動や個人的な取り組みを加点的に評価するのは一向に構わないのですが、現状の無試験型の入試は大学受験をした、受験勉強をしたとは到底言えるものではありません。国立大の推薦入試のように、共通テストで最低限の点数を設定するなどすべきです。
2、長い間中学で教師をやってた友人が、2000年あたりから、進学校に行く生徒がリーダーとして役に立たないと言ってたことを思い出します。人の世話より自分の勉強ばかりで、親もそんな感じだそうです。アメリカだと、名門大学に入るには、福祉関係の活動も必要とされます。
日本も子供の人口も激減なのだから、もっと余裕を持った教育ができたらと思うけど、益々中学受験など競争が激化とか、塾の多さとかあまりいい方向にいってないと思います。
3、私の経験から言えば、1980年代後半は、高校入試をはじめとする受験競争が激しくなるにつれ、子どもを取り巻く社会全体が「勉強」へとシフトしていきました。その結果、子どもが子どもらしく遊ぶ時間が減り、いわゆる“教育ママ”的な家庭が増えていったように感じます。偏差値だけが人生の成功への足掛かりとされる風潮の中で、「自分だけ」「自分のために」という価値観が強まり、どこか自己中心的な時代へと移り変わっていった雰囲気がありました。しかし、本来、社会を支えるのは学力よりも人としての力。いわゆる“人間力”です。偏差値だけでは社会は成り立たず、最終的には「地頭(じあたま)」の良さや、人との関わり方が優れた人たちによって支えられているのだと思います。学歴は一つの“ブランド”ではあっても、それがそのまま“本当の成功”を意味するわけではない。
4、慶應義塾の最大の問題はその学生の資質が、東大京大など旧帝大と一橋旧東工大には、全く遠く及ばないのに、プライドだけは異様に強いことだろう。
慶應三田会や慶應山脈などという考えがそれを如実に表している。いわゆる、中身はほどほどなのに勘違い輩を大量生産する。最近の新浪さんみればわかる。また、約40年?前に文系学部で数学抜きの入試を始めたことも完全にアウト。数学ができない人材は、主観で動く。俯瞰し合理的に行動できない。数学できない人材がトップにたつのは無理。本当に通用するのは、文学関係くらいだろう。経済人の育成を謳う大学が数学できない人材を世にだしてどうする?
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/d1520f83f20086e3b6df9b3e5372b19f8f543391,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















