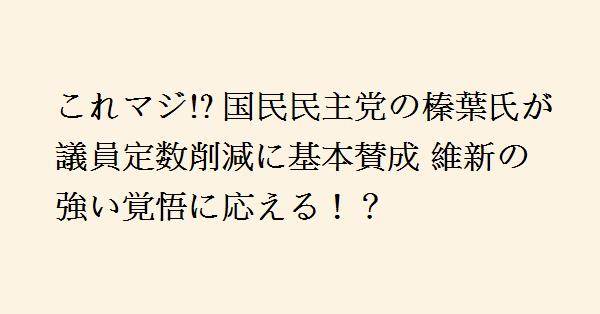
国民民主党の榛葉賀津也幹事長は10月23日、日本維新の会の中司宏幹事長らと国会内で会談を行い、衆議院の議員定数削減について議論を交わした。維新は自民党との連携を目指しており、比例代表の定数削減を検討していると表明。榛葉氏は「維新の強い覚悟を感じた」と語り、国民民主としても基本的には反対ではないとの姿勢を示した。しかし、具体案に賛同するかどうかについては、「選挙制度に深く関わる問題で、次の課題である」とし、その場では判断を留保するにとどめた。

政治制度の変革を目指して議員定数を削減する提案が話し合われたが、これには根本的な問題が存在します。まず、議員定数削減が本当に民主主義の進展に資するのか、疑問が残ります。代表の数を減らすことで、民主主義の代表性が損なわれ、国民の声が議会に届きにくくなる可能性があります。さらに、比例代表の削減が特定政党の有利性を増す可能性があり、政党の多様性が失われる危険性も考慮すべきです。改革を唱えるのであれば、まずは国民全体の意見を幅広く調査し、その結果を基に透明性のある議論を促進することが必要です。また、選挙制度そのものの改革と定数削減を同時に進めるべきで、その際には地方の声を取り入れることも欠かせません。最後に、議員数削減が本当にコスト削減につながるのか、経済的な影響を厳密に分析することが求められます。
抜本的な変革には、多方面からの考慮が不可欠であり、安易な削減は単なる表面的な解決に過ぎません。真の民主主義の進化を図るためには、国民の期待に応える真の議論と検討が求められています。
ネットからのコメント
1、定数を減らすだけでは無意味。選挙制度自体にしっかりと踏み込んでほしい。中選挙区の復活や3等身以内の親族が立候補する場合は、当該議員の選出される選挙区およびその隣接選挙区からの立候補は認めない、となど、改革してほしい。
2、榛葉幹事長が「議員定数削減に基本的には反対ではない」と発言したのは、国民民主党として柔軟な姿勢を見せたとも言えますね。比例代表の削減については「選挙制度に深く関わる」として慎重な姿勢を保っているのも、拙速な議論を避けたいという意識の表れでしょう。国民としては、数合わせのための削減ではなく、民意をどう反映させるかという本質的な議論を期待したいところです。地方の声が届きにくくなる懸念もある中で、制度設計には丁寧さが求められます。党派を超えて、納得できる形で進めてほしいですね。
3、安倍さんと立憲の野田さんとで定数削減を約束をしてから、もう13年以上経過します。
議員定数削減が実現しないと判断できる状態では、定数削減を主張する野党は多いのですが、いざ実現が見えてくると反対に転じることにはとても悲しい気持ちになります。国民への増税は慎重な議論なしに強引に進めるのに対して、自分たちの身分や収入が減りそうなことは慎重に議論する必要があると主張し、結局は実現せずそのまま終わります。今回こそ実現すべきであり、反対する政党はどこなのか国民は注視しましょう。どうか、建設的な議論をお願いします。
4、選挙制度は民主主義の根幹を成す重要な制度です。世界において独裁政権が自分たちに都合の良い選挙制度に変えて独裁を強化したケースは多いと思いますが、自維連立政権にはくれぐれも自分たちに都合の良い制度に自分たちだけで変えるような独裁手法を取らないようにして欲しいです。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/55636ce07e0534be9c709d67e3ba86825b603652,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















