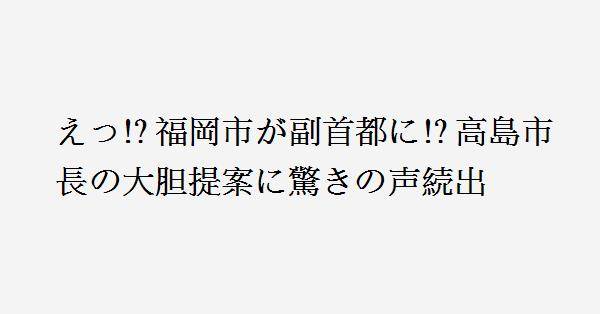
福岡市の高島宗一郎市長は22日の定例会見で、日本維新の会と自民党の連立合意に基づく副首都構想について言及しました。彼は、福岡市が首都のバックアップ機能を担うのに適した場所であるとし、その理由として南海トラフ地震による同時被災のリスクが少ないこと、交通の便や事業継続計画(BCP)の観点から福岡市が適切であることを挙げました。
しかし、副首都構想が具体的に省庁の移転や都市の再編、統治機構の調整を意味するかどうかは今後の議論次第としています。連立合意文書には、副首都の機能の整理と多極分散型経済圏の形成を進めるため、2026年通常国会で関連法案を成立させることが明記されています。

現在の副首都構想は、緊急時に東京に代わる機能を持たせることが目的として提示されていますが、その実現には多くの課題が潜んでいます。まず、制度設計の欠陥があります。福岡がバックアップ機能に適しているとする地理的な理由は理解できますが、それだけで副首都に求められる要件を満たすわけではありません。次に、具体的な省庁移転や統治機構の再設計に向けた詳細な計画が不透明であることが問題です。これを受け、解決策として、第一に、市民や専門家を交えた公開討論の場を設けることが急務です。
第二に、緊急時の迅速な行政対応を可能にするための具体的な法律作成を推進するべきです。第三に、ITインフラの強化によるリモートワークの拡充で、多極分散型経済圏への移行を円滑にする策が求められます。副首都構想が真に国民の安全と経済の安定を担保するものとなるためには、透明性と具体性を持った施策が不可欠です。さもないと、ただの理念に終わる恐れがあります。
ネットからのコメント
1、バックアップ機能でいえば、大阪だけじゃなく他にも分散したほうがいい。たとえば関東だけじゃなくて近畿九州にも分ければリスク分散になる。維新の吉村さんが望むような大阪の地位向上にはならないけど
2、福岡いいと思う。府知事がどう言うか分からないけど、災害時を想定するなら大阪は東京に近すぎて意味ないと思う。九州も最近は地震多いけど、そんなのは日本列島どこもリスキーだし、東京との相互影響がないとこがいいはず。あと西日本に雇用がほしいから。
3、高島福岡市長の意見にも一理あるが、東京に続く日本の都市はやはり大阪というのが否定できない事実でしょう。南海トラフ地震などで東京、大阪が同時に被害に遭うことは想定したくないですが、リスクを分散する意味では副首都なり首都パックアップ機能なりを2,3箇所に分散しておくことは悪くないと思います。
そう考えれば、①大阪、②福岡、③札幌などに分散するプランを検討するのは良いでしょうね。
4、福岡市民ですが、確かに東京との同時被災の心配は無いものの、市内中心部を警固断層が走っているので、自然災害に強い都市とは言えないように思う。また、有事を考えると東アジアの他国からの距離も気になる(それが経済的にはメリットになっている面もありますが)。個人的には岡山あたりが適切のような気もします(広島も悪くないですが、やや豪雨災害に弱いイメージ)。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/acb6d12386e74c5a639952a6fac24308ef9db4fb,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















