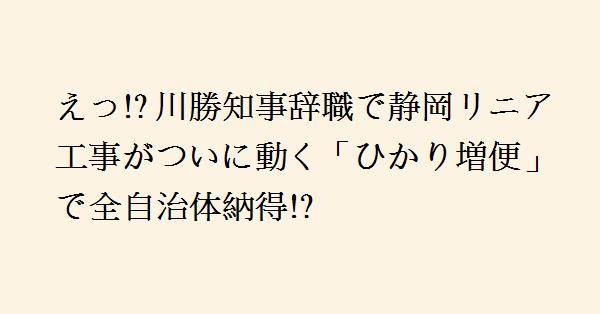
2026年度中に着工が見込まれる南アルプストンネル静岡工区に関する報道。リニア中央新幹線の建設が進む中、唯一工事がスタートしていない静岡工区では、大井川流域の水資源や生態系など環境への影響が懸念されていた。これを解決するためJR東海は全水量を戻すことや補償文書の取り交わしなど、流域市町と県との調整を進めている。
自治体側は補償請求期限を設けず、JR東海が負担する費用に上限を設けないこと、国や公的機関の関与を求めるといった条件を提示。環境影響モデルには課題も残るが、鈴木康友知事は交渉へ前向きな姿勢を示しており、問題解決が進む兆しが見え始めている。補償文書の締結により着工への条件は整う見通しだが、「ひかり増便」という地域振興策が流域市町を納得させるかが鍵となる。

リニア工事による南アルプストンネル静岡工区の着工がいよいよ現実味を帯びてきた。しかしながら、その背景には複雑な問題が横たわる。環境への影響が懸念される中、大井川流域の水資源や生態系がどの程度の負荷に耐えられるのか、確固たる科学的根拠に基づいた結論は未だ得られていない。そのため、JR東海が示す補償案がどれほどの効力を発揮するのかは未知数だ。
問題の核心は、工事の環境への影響が実際に顕在化した場合に発生する責任とその対応だ。一部地域では既に工事に起因するとされる被害が報告されており、このような事象への慎重かつ透明性の高い対応は必須である。しかし、補償についての文書はまとまったとしても、長期的な環境影響への予測や地域住民の不安解消はまだ十分とはいえず、自治体間の意見の調整が課題のままである。
解決策としては以下の対策が求められるだろう:
地元住民や首長への丁寧な説明を含む対話の場を定期的に設けること。着工後も十分な環境モニタリングを行い、迅速な対応策を保証すること。住民に具体的なメリットを実感させる地域振興事業の立案と実施。リニア工事は先進技術の象徴として期待を集める一方で、自然環境や地域との共生が軽視されれば、未来を築くプロジェクトは根本的な矛盾を突きつけられるものとなる。技術進歩が犠牲を伴うものではなく、調和と持続可能な発展の道筋であることを示すべきだ。静岡工区の着工は、信頼と責任が試される瞬間である。
ネットからのコメント
1、リニア工事からの想定被害について分かっている方々は川勝知事の反対していた意味は理解していたと思います。
現在は意味が分かっていない方が判断しているようなので間違いなく大井川は枯れると思われます。現状でも農家さんが使っている大井川農業用水が足らない時があるので工業用水を使用している企業さんも考えておかなければならない問題です。JR東海は本当にわかっているのか心配です。川勝知事が行って来たことは妨害ではありませんよ。
2、「妨害」という書き方に偏向を感じる。感じ方は人によるだろうが、着工区間で様々な異変が起きているのは事実で、そういったことにJR東海は誠実に向き合ってこなかった。例え異変が起きても、個人や小さな団体が原因を突き止めるなどまず不可能。多くの人のメリットの陰で、生活に直結するようなデメリットを被る人が出てはいけない。
3、南アルプスを貫通するトンネルが10年で完成するとは到底思えない。中部横断道でさえも富士川上流域は、かなりの軟弱地盤で想定外の湧水が大量に出て、開通が10年近く遅れた経緯を考えれば、リニアの品川ー名古屋開通は2050年以降だろう。その時に交通インフラがどのように変わり、新幹線の何倍も電力を買うリニアの必要があるのかね?賭けでしかないよ。
4、川勝知事の多大な貢献でリニアの根本的な工事の遅れを誤魔化す事が出来たわけで現在の遅れはJR東海の見通しの甘さですから 改めて川勝前知事に感謝しましょう
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/2e02fa9191aea03ab40a14a417fa01fb10753ea8,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















