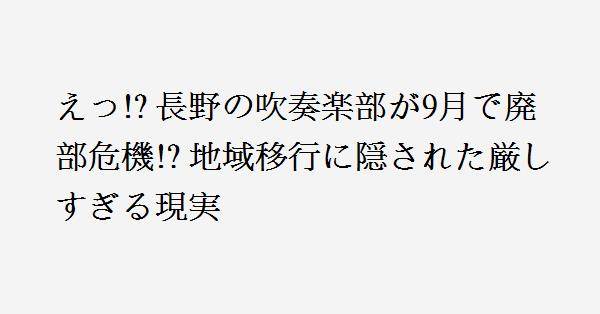
事件概要:長野県内の公立中学校で進められている部活動の地域展開(地域移行)により、多くの吹奏楽部が廃部となる予定であり、移行先の支援団体や施設、指導者の確保が難航している。長野市内では、吹奏楽部が19校中14校で9月末に廃部され、移行先の民間クラブ「長野ジュニアバンド」が受け皿となる。練習場所や指導者不足が深刻で、特に郊外の生徒は通学の問題を抱えている。
さらに、学校が貸し出していた高額な楽器の維持管理に関しても不透明な部分が多く、移行後の活動に支障をきたす可能性が高い。

コメント:吹奏楽部の地域展開は、文化系部活動の特殊な課題を浮き彫りにした。施設不足や指導者不足は、地域移行の最も深刻な問題であり、文化芸術に対する理解と支援が欠けていることを象徴している。現状のままでは、若い才能が活躍の場を失い、地域文化が衰退する懸念がある。まず、地域の公共施設をフル活用し、音楽専用の練習場を確保するべきだ。次に、地域内での指導者の養成と協力体制を整え、外部の元教員や音楽家の支援を得る仕組みを作る必要がある。また、高額な楽器の維持管理については、市や学校、地域が共同で負担する体制を築くべきだ。文化系部活動は地域社会の宝であり、これを放置することはその価値を無視することに他ならない。
ネットからのコメント
1、柳沢教諭は「関係者で話し合いを続けているが、タイムリミットが迫り、困っている」と漏らした。こうやって、地域移行にまで教員がかかわらなければならない。結局子供のためだからなのである。ここまで何十年も、子供のためだから、子供の受け皿が必要だからと、中学校で部活動が続けられてきた。本来部活動は中学校や高校の仕事ではない。しかし、勤務時間のかなりの部分を部活動が占めている。今、地域移行にこぎつけようとしているところだが、結局移行事務も全て教員が負担しているではないか。結局教員頼みの依頼体質社会なのだ。何かあれば学校。すべて学校に負担を押し付けて、学校や教育委員会が全く断らなかったことが原因なのだ。保護者も社会全体も、教員はしてくれて当たり前と思い込んでいる。そここそがおかしいのだ。
2、学校の吹奏楽部は長い間、教員のボランティアで支えられてきました。休日も地域行事の要請があれば、仕方なく出向いてきました。その代りに、地域の学校振興会のような所から、支援金を頂いていました。しかし、これらも教員の過重負担や、少子化などの影響で限界に来ています。
吹奏楽部は、学校の部活動での継続は不可能だと思います。
3、今年も吹奏楽コンクールが始まっています。8月中までに県大会、9月に地方大会、そして10月に全国大会と続いていきます。吹奏楽連盟は、少人数でも音楽が成り立つように楽譜を作成段階から考慮して作っている(今年は連盟の委嘱作品2曲ありますが、皮肉なことに超不人気)ようですが、上位に進んでいくのは大編成の学校ばかり。何年か前、小学生の東関東大会を聞きに行きましたが、県によってレベルの違いが素人でも分かるほどはっきりついていました。今後、中学、高校と都市部と地方との差がどんどんついていくと、吹奏楽離れはさらに進んでいくことになるんでしょうね。吹奏楽ファンとしては残念なことです。
4、以前小学生の吹奏楽クラブのニュースを見たが、楽器以外にも練習場所探しや楽器の保管、移動にもとんでもないくらいにお金がかかり、有料演奏会をしたり、クラウドファンディングをしているとあった。中学校の部活動はそれを全て部活動の名のもと無報酬の教員も使えてやってこれたが、はたして今後はどうなっていくのだろう。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/d4b740401ff9cf03ebd4153169e9443d6978fc2c,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















