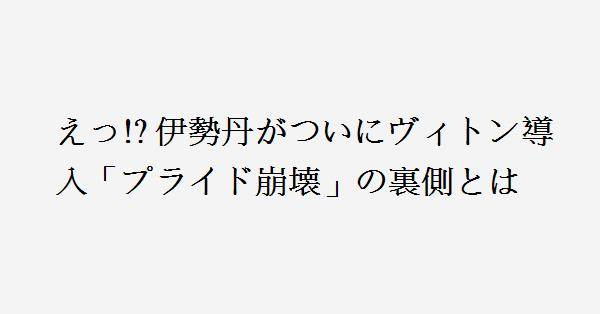
三越伊勢丹HDは、伊勢丹新宿本店が2025年3月期に売上高4212億円と過去最高を記録した一方、地方店は過去10年で約50店が閉鎖され、業界全体の売上は1990年代初めの約10兆円から半減。衰退の背景には、利益率3〜5%台という構造的低収益、消化仕入れ依存、富裕層とインバウンド頼みの経営などがある。かつて本館に高級ブランドを入れない方針を貫いた伊勢丹も、2024年11月にルイ・ヴィトンを導入。
大西洋元社長は2009〜2017年に仕入れ構造改革や地方再生を試みたが、組織内部の抵抗や地方店閉鎖で成果は後退し、業界は新たな転換期を迎えている。

百貨店の凋落は単なる消費者嗜好の変化ではなく、長年放置された構造疲労の結果だ。利益率の低さを放置し、中間業者依存で自らの仕入れ・販売責任を放棄した経営は、リスク回避の名の下に現場力を削ぎ、独自性を失わせた。富裕層と観光客頼みの繁栄は一時の蜃気楼に過ぎない。今必要なのは、①中間流通を大胆に省いた直結型の生産・仕入れ体制の構築、②地方生産拠点との共創による「日本製」ブランド力の再強化、③現場と中間管理層を橋渡しする意思決定の迅速化だ。百貨店は、文化と商業を結ぶ公共的存在であったはずだ。そこから逸れた瞬間、単なる「高級テナントビル」に成り下がる。
今こそ、かつての誇りを背負い直す覚悟が問われている。
ネットからのコメント
1、スーパーが普通の日の物を買う場なのに対して、百貨店は「ハレの日」の物を買うイメージです。イギリスやパリなどでは日本なんかよりも老舗の名門百貨店がありますが、ここの主たる客層もアジア人・アラブ人です(オーナー自身からしてエジプト人やインド人だったりします)。日本の百貨店もまだインバウンドでも魅力に思って来てくれるだけ恵まれていると思いますよ。スーパーと同じ物を売ってては百貨店は負けます。ぜひ百貨店ならではのちゃんと「粋」や「雅」を熟知した頭一つ分上を行く商品やサービスを提供してほしいものです。いい意味で頑固になってほしいな、と思います。
2、デパートはかつては安心して高い買い物ができる非日常的な場所でした。デパートごとにブランドが確立していて、そこの包装紙でくるまれていれば、何を選んでもあげた人に喜ばれていました。ですが、今は百均はあるはユニクロとかのファストファッションもあるは、JINSとか安売り眼鏡店はあるは、場合によってはドンキも入っています。
街のショッピングセンターと同じようなお店の構成になっていて、ほとんど今やテナントビルに成り下がってしまいました。できることなら、夢のある非日常空間をウリにするかつてのデパートを戻って欲しいです。屋上遊園地とか屋上動物園とか、今なら復活してもそれなりの需要はあると思います。安全基準とか許可の基準が今と昔ではちがうので難しいとは思いますが、、。
3、百貨店はもはや時代錯誤になってきている感が否めない。都市部のターミナル駅百貨店は別として地方百貨店はもはや限界になってきている。フロア丸ごとをニトリやロフトに賃貸ししたりして運営しているが、それならばイオンモールやららぽーとなどに行った方が広大な駐車場も有り車も停めやすい。地方百貨店は未だに激狭の立体駐車場を改善出来なかったり、近くのコインパーキングを提携して買い物サービス券で対応しているが、いかんせん駐車場から百貨店店舗までの距離が遠い所が多い。駅前の限られた土地使用がそういったハード面の改善も妨げていると思います。
4、節目節目の時にはデパートに買い物に行く。
それがステータスな時代がありました。今でもプレゼントや何か手土産の際はデパートで買うという事はありますが、それは薄れてきています。私も幼い頃はおめかししてデパートに買いに行き、子供の節目を親は感じながら成長も合わせて祝っていたと感じます。普通のサラリーマン家庭でしたから、進学や就職の際、洋服やコートなど買う時に、値段を見て安い方を選ぶと、「遠慮するな。その代わり長く使えるものにしなさい」と両親から必ず言われました。社会人になった頃に買ったコートやスーツは20年近く着用できました。もうじゅうぶんだねと、破棄する際洋服を眺めながらその当時の話しを母がしていました。贅沢な時代だったと感じるのと同時に、親の愛情も改めて実感しました。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/5319d3ce570695b5ca47173ecd1b297987a5f112,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















