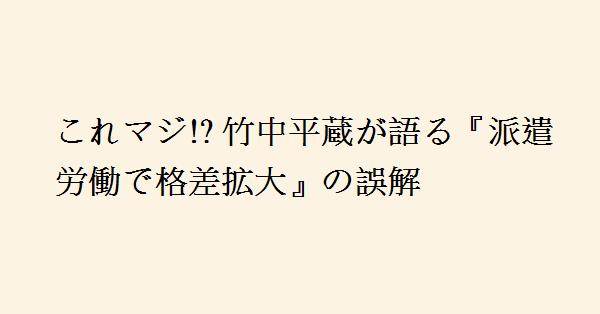
事件概要:2024年、日本の競争力ランキングは38位に沈み、経済学者の竹中平蔵氏は日本の制度的な欠陥が雇用市場に影響を与えていると指摘。特に、終身雇用の崩壊や派遣労働の増加により、労働市場が固定化されていると批判する。派遣労働の導入は、1997年にILOが採択した「民間職業仲介事業所に関する条約」に基づいており、派遣労働者の割合は依然として低い。
しかし、格差拡大の指摘は誤解だと主張。制度改革の欠如と、バブル崩壊後の検証不足が日本の経済停滞を引き起こしている。

コメント:現在、日本の労働市場と経済政策における根本的な問題が浮き彫りになっている。竹中氏が指摘するように、終身雇用制度の崩壊に伴う雇用の流動性の欠如は、働き手にとって極めて不利な状況を生み出している。しかし、この問題は個々の企業や労働者の責任だけではなく、制度の欠陥に起因している。労働市場を活性化するためには、以下の改革が急務だ。
金銭解雇の導入:労働者が簡単に職場を変えられるようにするため、解雇に関する明確で公平な補償制度が必要。派遣労働の規制強化:派遣労働者の待遇改善を図り、より安定した職業選択を可能にすべきだ。検証機関の設立:過去の経済政策やバブル崩壊の検証を行う専門機関を設立し、今後の政策改善に役立てるべきだ。日本社会の制度的な横並び意識と労働市場の不透明さは、経済の低迷を続けさせている。改革なくしては、将来的な成長は望めない。
ネットからのコメント
1、派遣社員の給与は正社員よりも日給を高くする制度を導入するべきであった 社会保障費は派遣先の負担にするべきであった 竹中氏は、手取りの給与の事は考えてない 社会保障費の負担を派遣社員に負担を負わせる事をさせるべきではなかった 派遣社員は、1990年に世界一高かった人件費削減を経団連から求められて決まった事 人件費削減よりも設備投資を促す政策をしない企業よりの考えを竹中氏が実現した 政治献金が、派遣制度を作ったと言っても過言ではない
2、終身雇用は一億総中流を産み経済や社会は安定して明るい未来でした。小泉政権下の竹中さんの雇用の緩和は、非正規雇用を蔓延させ、今では若者層まで浸透しました。恋人がいながら低年収で結婚出来ない若者増え、結婚率の低下は少子化の一因だと思います。正社員1人で非正規雇用3人雇えると言われ企業に都合の良い政策ですが、非正規雇用では住宅ローンさえ難しいです。
竹中さんの雇用の緩和は今日の日本に何をもたらしたのだろう。究極の移民政策かも知れませんね。
3、>終身雇用・年功序列こそが唯一の正しい働き方であるという考え方は、労働者を会社に閉じ込めていることにほかならない。そのような不公平なことがあってよいはずはない。だからルールをつくる必要がある。実際小泉改革で派遣法が改正された後、それまで50万人程度だった派遣社員の数が数年で150万人まで膨れ上がった。企業にとっては良かったかも知れないけど、労働者にとってはどうだったのだろう。本当は正社員で働きたかった人も、仕方なく派遣社員になった人も多かったのでは。でも、それでもきちんとした報酬が有れば良かった。けど実際は派遣会社のピンハネが多く、雇った企業の半分を派遣会社が取っていたとの話もよく聞く。結局、小泉改革で一番儲かったのは派遣会社と思う人は多いと思う。そう言えば、竹中氏ってかつて大手派遣会社の会長でしたね...。そりゃ、小泉改革を正当化したいだろうなと思うけど。
4、派遣労働者のほうを解雇されやすくしてしまったのは事実であろう。
やるなら正社員も同様にするべきだったのだ。そうすれば氷河期世代も発生しなかっただろう。派遣と新規採用が調整弁に使われていたのだから。所得格差の度合いを測る指標として使われる「ジニ係数」は、1990年代から2000年代にかけてほぼフラットに推移しているというのは説明不足だ。実際の「当初所得ジニ係数」は拡大を続けており、税のもつ所得再配分機能をつかって調整後のジニ係数をフラットにしていただけで、「稼ぐ力の格差」は拡大する一方だ。派遣のようなカースト制度みたいなことを作ってしまうからそうなるのだ。脱線するが、税は所得の再配分に使われて修正後のジニ係数はフラットなのは事実だ。これは消費税で賄えばよいが、実際に赤字国債で賄われる結果物価は上昇して格差は解消されない。格差を減らすには減税などやってはだめなのだ。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/5c1c9986c124c79f97303cb459facdd4f81b8935,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















