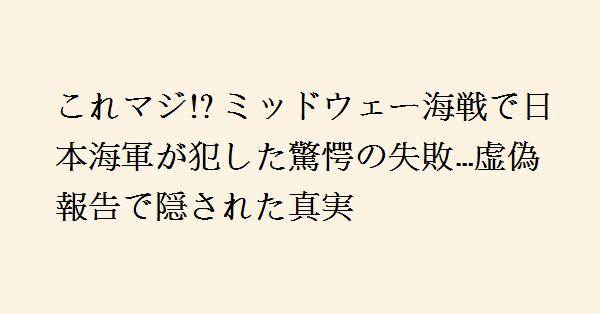
事件概要:1942年6月5日、昭和17年のミッドウェー海戦が北太平洋中央部のミッドウェー島沖で発生。日本とアメリカの機動部隊が激突し、日本は空母4隻(赤城、加賀、飛龍、蒼龍)と200機以上の航空機を失う大敗を喫した。日本海軍は勝利を確信していたが、戦局は予想外の展開となり、空母部隊の壊滅は戦争の作戦遂行能力を大幅に損ない、結果として日本は敗北へと至った。
この敗北は太平洋戦争のターニングポイントとなり、その後の戦局を決定づける重要な出来事となった。

コメント:ミッドウェー海戦の結果、日米の海軍力における逆転は、日本の指導層が持っていた過信と戦略的誤判断が生んだ悲劇に他なりません。最も顕著な問題は、作戦の目的が不明確で、実行における優先順位が曖昧であった点です。さらに、日本海軍は敵状の把握を怠り、過信のあまり、無理に作戦を推し進めてしまいました。結果として、膨大な兵力を失い、戦争の展開に取り返しのつかない影響を与えました。ミッドウェー海戦での教訓は、戦争という極限状態において指導層の決断がいかに重要かを浮き彫りにしています。戦後、日本の海軍は失敗を隠蔽し、教訓を活かすことなく次の戦闘へと進んでいきました。このような反省のなさが、更なる無駄な敗北を招いたことは明白です。
ネットからのコメント
1、まあ、太平洋戦争はこのミッドウェー海戦が全てである。日本の唯一の勝機を逃しただけでなく、敗戦を決定付けたのもミッドウェー海戦である。山本五十六は真珠湾で逃した米空母を全滅させ、早期講和に持ち込むしか日本の勝ち目はないと良く分かっていた。空母4隻と歴戦のパイロットを一挙に失い、山本は茫然自失で戦意を喪失した。後は転がるように広い太平洋で負け戦を重ねただけである。敗因は様々に研究されているが、山本が乗った戦艦大和の主力艦隊が何故500キロ以上も後方にいたのか?これでは海戦に参加していないのと同義である。米軍が持てる戦力を集中させたのと対称的であり、戦力を分散させるのは真に愚の骨頂である。歴史にもしはないが、山口多聞少将の意見を取り入れ大和以下の戦艦群で4隻の空母を守る輪形陣で出撃していれば、結果はまた違ったのではなかろうか?山本が遥か後方の大和から高見の見物をしているようではダメなのである。
2、米空母を発見し、より大きな戦果を上げるため、陸上攻撃用の爆弾から、艦船攻撃用の魚雷換装中に敵機の攻撃を受けて空母が沈んだ、というのが定説だった。
しかし最近の研究では、南雲中将以下艦隊司令部は付近に空母があるはずはないと考えて、陸上攻撃を主と考えていたこと、敵機の練度から空母を沈められるとは考えていなかったため、空母がまとまって行動していた。日本の陸海軍とも、英米軍を侮ること甚しかった。真珠湾を含む戦いでの、機動艦隊の魚雷や爆弾の命中率は8割を超えたという。大戦中新たに就航した空母は日本は数隻しかなく、しかも稼働前に沈んだ艦もある。優秀な搭乗員の育成には時間がかかり、また教える側の教官も少ない。練習用の機材や燃料も足りず、ミッドウェイ後、開戦時の練度を取り戻すことは出来なかった。
3、「勝ちに不思議の勝ちあり。負けに不思議の負けなし」という言葉が、これ以上なく当てはまるのがミッドウェー海戦。日本軍の敗因は文中にもあるが・ミッドウェー占領と敵空母撃滅の二兎を追った戦略の問題(最初から敵空母撃滅を主目的にしていれば、兵装転換は発生していない)・ダッチハーバー攻撃に空母を2隻割き、足手まといでしかない戦艦部隊の護衛にも空母2隻を割くという、戦力集中の原則に完全に反した配置をしたこと(8隻がそろっていれば、こちらも損害を受けても敵空母を撃滅は可能)・敵を完全に見下し、例えば米軍を発見すべき位置を飛行する索敵機など、どうせ大丈夫という甘えから雲上を飛行し、敵を見落としたこと・内容が不完全であったとしても、他の機の報告で敵出撃を感知した時点でまだ運が残っていたのに、索敵強化等適切な対策を打たず時間を空費したこと戦力的には優勢でも、負けるように戦っていたとしか言えない。
4、仮に、ミッドウェー海戦での空母の損失が少なく、ミッドウェイ島攻略に成功したとする。だが、そこは制海権ぎりぎりの孤島、逆に地図を見るとミッドウェイ島はハワイ諸島の延長線上の島。ミッドウェイ島はハワイからのB17の空襲に晒され、本土からの占領部隊への補給艦船は、米海軍潜水艦の餌食になり占領部隊は徐々に疲弊。遅くとも、米海軍が機動部隊を再編・増強する1944年には、何回かの機動部隊の海戦を経て、彼我の力の差が顕著になり、ミッドウェイ島がガダルカナル島になっていただろう。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/13aeab2e2713de69cd5efc05940b437f2d26d012,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















