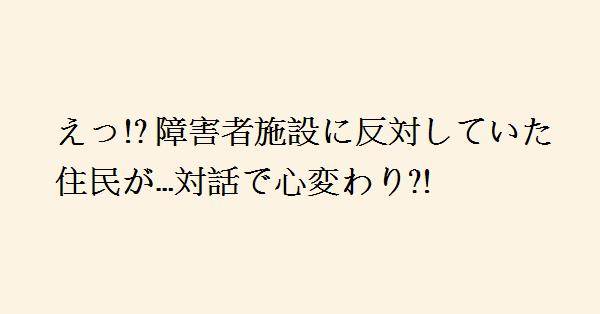
障害者施設の建設が住民の反対に遭うケースが増えており、その背景には障害者に対する無理解があることが指摘されています。特に都市部では、障害者施設の設置に対して治安悪化や地価の低下を心配する声が多く上がり、地域住民との対立が深刻化しています。元代議士の山本譲司氏は、障害者施設建設に対する反対運動が地域社会において、障害者への理解不足に起因していると述べています。
山本氏自身、地域住民との対話を通じて障害者への理解を深め、共生に向けた前向きな変化を促した事例を紹介しています。また、自治体における福祉政策の不備も問題視されており、障害者の社会復帰を妨げる要因となっています。

地域住民と障害者施設の建設に関する対話を重ねることで、理解が進み、共生の道を開くことが可能であることを示唆しています。このような事例は、社会全体での障害者理解と支援の重要性を再認識させます。
ネットからのコメント
1、介護職です。事業所がデイサービスを新設しようとしたときも、少なからず地元の反対意見はありました。ただ真摯に対応し室内を公開するなど歩み寄り、ある程度の理解はいただけたと思います。記事に『障害のある人は、もともとおとなしい性格だけど、人にだまされたり、生活に困ったりして、やむなく罪を犯してしまうことが多いっていう話だ』とありますが、残念ながら困っているから犯罪に行く時の垣根が、健常の方よりも低いのが障害のある方です。
障害福祉に深く携わる人にありがちな、なぜみんな障害者を理解してくれないのだという思いは、実は携わる側が、みんなが障害者の何に不安を抱いているのかを理解していないからなのだと思います。一方的に障害者を理解して欲しいはあまりにも横柄。これは差別の問題ではなく、お互いが歩み寄る必要がある事だと感じます。
2、社会福祉施設で働いていますが、実際問題として近隣住民に迷惑がかからないわけではありません。徘徊や奇声、問題が発生すれば警察を呼ぶこともあります。これらを迷惑と解釈する前に彼らを少しだけ理解してほしいと思います。前述の迷惑かもしれない行為は知的精神の障がいに関係なく、認知症の方は徘徊しますし酔っ払いや痴話喧嘩でも怒声や奇声は発します。偏見を完全に払拭しようと思わないけど無理解や誤解から発生する偏見だけは無くす努力をしています。彼らの世界を広げるには地域住民の協力より理解が必要だと思います。
3、近所の障害者施設は、缶と古紙と段ボールを24時間出してもいいし、庭や畑でとれた野菜を安く売ってくれるし、とってもありがたいよ。
時々わーって声が聞こえたりしてはじめはビックリしたけど今は慣れてもう耳も反応しない。施設職員のかたは感じがいいし、利用者さんは時々散歩してたり、敷地内で作業したりしてるけど嫌だなと思うようなエピソードは今のところないな。私のくる前からあったから順応したけど、後から建たるって話ならどうだったかな。色々助かることもあるって知らなかったらただ反対しちゃったかも。
4、障害をお持ちの方は差別されるべきでは無いです。ただ、以前ホームの電車待ちをしていた際に、明らかに脳系の障害をお持ちの方が間近で同行者の顔を下から覗き込むようにしてきたり、一般の常識と異なる行動をされることがあります。彼らは差別されるべきではありませんが、彼らによって健常者が不自由を強いられるべきでもないと私は思います。程度にもよりますが棲み分けが必要に思います。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/7d7cb0a984b0e62bd465bc31e7e544ee79391ff5,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















