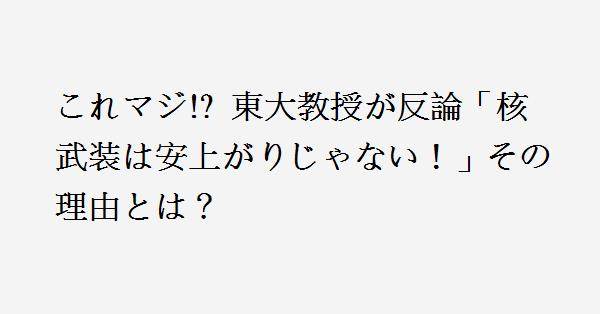
東大公共政策大学院の鈴木一人教授がABEMA報道番組に生出演し、参政党の塩入清香氏が発言した「核武装は最も安上がり」に異論を示しました。鈴木教授は核兵器の抑止力に基づく意義を説明しましたが、「コストパフォーマンスは悪い」と断言しました。核抑止が成立しても通常兵器による戦争がエスカレートし、結果的に核を持つことが紛争抑止につながらないと指摘しました。
またアメリカが核と通常兵器に巨額を投入している例を挙げ、「全然安上がりじゃない」と強調しています。

核兵器が「安上がり」とする無責任な発言には重大な批判が必要です。このような主張は核抑止力に関する無理解を招き、誤った政策選択を助長します。鈴木教授が示した問題の本質は、核に限らず通常兵器の戦争がエスカレートするということです。核兵器と通常兵器の保有が不可避である現状は、平和構築における根本的課題を浮き彫りにしています。まずは国際社会が非核化への明確なロードマップを設定し、軍拡競争を減少させることが必要です。さらに各国政府は安全保障の新しい枠組みを築くための対話を深化させるべきです。市民に対しては軍事費の透明化と充実を確保することで、政府の責任を問い続けることが求められます。このような論理的で具体的な行動が平和を保障するための鍵であり、核武装が「コスト安」などという幻想にとらわれない現実的な価値観への痛快な結論を導くべきでしょう。
ネットからのコメント
1、核を持っていても通常兵器は必要なので安上がりにはならない。はその通りだと思う。でも、核を持っていない国に対しては核の懸念なく攻めることができる。逆に核を持っている国は脅しが効く。ロシアが核を使うことは無いだろうが、チラつかされただけでEUは敏感に反応していた。どう考えても抑止力はある。国防に於いては、やるやらないではなく全ての手段をテーブルの上に於いて置くべき。手段を絞ること自体が相手を利する。核の議論をするだけで叩かれるような状況は敵対勢力を喜ばせるだけ。
2、核はその運搬手段も含めると維持費は非常に膨大なものになろう。一方で核があれば削減できる通常兵器というのは意外と無いのかもしれない。なので単純に防衛費の面から考えたら核はコスパが良いとは言えないだろう。ただ通常兵力が強大であったウクライナが易々とロシアに攻め込まれたように、通常兵器だけでは防げない戦争と言うものがあることも事実だろう。そのための核という考え方は十分にあり得るし、核を含めた日本に相応しい防衛を議論することは重要である。
3、ウクライナは核を保有していない為にロシア本土への攻撃がほとんど行われていない事例は見れました。しかし核を持っていて大規模戦争になった場合、核戦争になった可能性はあります。ただ核保有国同士の大規模な戦争は今のところ起こってないので、やはりウクライナが核武装していればここまでの大規模な戦争にはならなかった気がします。つまり核保有は戦争自体を抑止する効果はあると思うので有事の損失を考えればコストは安い。ただし総力戦になった場合のリスクは計り知れない
4、太平洋戦争で唯一使用した当時のアメリカを除けば、核を使用するのは、その報復リスクからその国の体制や政治指導者の政治生命、多数の国民の生命をかけて行うレベルになっていて、あのイスラエルでさえイランからの報復ミサイル攻撃を受けて、その反撃に核を使用していないし、頻繁に衝突しているインドとパキスタンも使用していない。通常の軍事紛争では通常兵器を使用するしかない状況にあり、近隣と紛争リスクのある国は通常兵器を削減することはできない。むしろ核を持つということは、その開発、製造、管理コストが莫大になり、純粋に軍事費の増大をもたらすことになる。
しかも、周辺国との緊張感を高める結果となり、その対応のために通常兵器を含めて強化せざるを得なくなる。加えて、経済制裁を受ける可能性も高い。食料や原油、レアアースが入ってこなくなり、すぐに干上がるだろう。参政党の議員の見識の浅さがよくわかる。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/ca03046e357ebc1d8028bc84a01a1129a8f7a00c,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















