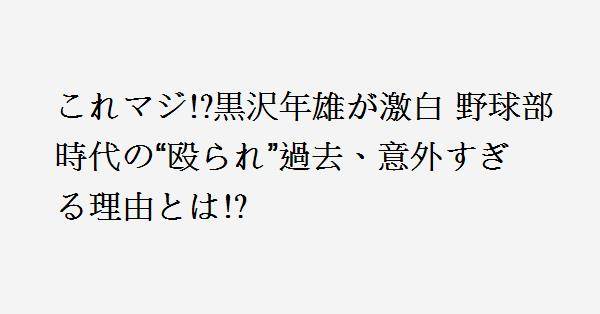
黒沢年雄(81)が、自身のブログで、中学・高校時代の野球部で受けた体罰について語りました。彼は「暴力を肯定する訳ではない」としつつ、当時は殴られることが常識だったと述べています。「憎しみは全くない」とし、当時は怒られることに慣れており、殴る方も怪我しない程度に行っていたと回顧。昨今の教育では、大声で叱ることも難しい現状に触れ、「おかしな時代」だとしつつ、躾の責任は親にあり、愛情を伴った躾が必要だとの持論を展開しました。

この出来事には深い考察が必要です。まず、黒沢氏の回顧には、昔の体罰が当たり前だったという認識の提示があります。しかし、体罰が常識とされる環境が正常であったかどうかは疑問です。そもそも、体罰を教育手法とすること自体に大きな問題があり、教育現場の倫理観が欠如しているといえます。現代の教育では、言葉や態度でしっかりとしたコミュニケーションを図り、子供たちの理解を深めることが求められています。そこで、以下の解決策を提案します。第一に、教師や指導者には適切な教育技術を身につけるための研修を義務付けます。第二に、親と教師の連携を強め、家庭と学校の教育方針を一致させます。第三に、子供たちが自身の感情を表現する場をもっと設けることで、互いに理解し合う環境を作ります。これにより、愛情を伴った教育が可能となり、体罰に頼らない教育の実現が図れます。
暴力と教育の間に明確な線を引き、安全で信頼しあえる社会に向けた取り組みが急務です。
ネットからのコメント
1、基本的には暴力には断固反対ではあるが、何度注意しても、馬耳東風で聞く耳を持たず、どうにもならない人間の態度を改めさせるために、当人が痛い目にあって、自分の行いを見つめ直させるという経験が必要な場合はあると思う。昔は暴力が時にはその役割をはたしていたと考える。現在はどんな理由があっても、暴力は許されない風潮だから、暴力以外の方法で、教育的な指導を行わなければならないが、なめた態度を取り続けて、口で言ってもどうにも分かり合えないような人間にはどうすればいいのか。もうあきらめて放置しかないんだろうなと思う。
2、この問題を突き詰めると、戦中の教育に辿り着くと思います。私の子供の頃は、大人は戦争経験者でしたので、教師も指導と称して殴るのが当たり前でした。中学の時に、クラスの男子の万引きが見つかったときは、連帯責任として学年全員の男子が正座させられました(その生徒は卒業以来会っていないです)。教師の中で暴力が一番ひどかったのは、戦争に行かなかった戦中世代だと思います。
シベリア抑留から生還した祖父は、戦争で一番辛かったのは上等兵の虐めと言っており、戦争を忌み嫌って、威張って自分や他人の子供や孫を殴るようなことはしませんでした。
3、私も学生時代野球をやっていました。怒られることもあったし、殴られることもありました。私はどんな理由があっても殴るのはダメだと思っており、上級生になっても殴ることはしなかったです。このコメントは広陵の件があってのことだと思いますが、広陵の件は、集団リンチなので、躾とかのレベルでは無いよね。
4、両方とも極端すぎる。今の怒れない親も問題はあるけど、昭和前期世代のちょっと何かが起こると若者や後輩を殴る・怒るが当たり前というのもかなりの時代錯誤。水を飲むなとか無駄な関係の先輩後輩なども戦争の影響はあると思うけどさすがに戦後80年。もう卒業しないと。特に多くの運動部と昔ながらの社風を第一に考えている企業。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/7e7cfa0577323aa477d7c0ac011232d87c403e3a,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















