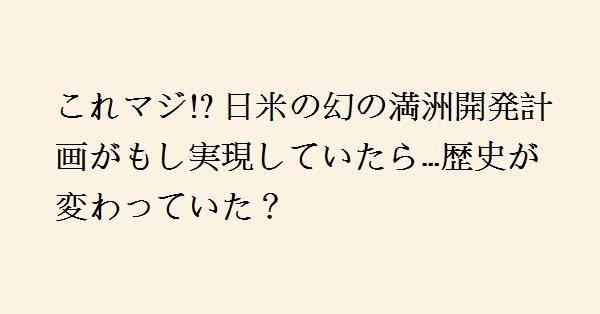
この記事では、日本が太平洋戦争を起こすに至った歴史的背景を、近代史研究者の辻田真佐憲氏が論じています。当時の日本は、潜在的な資源不足や英米への不満から、戦争という選択をせざるを得なかったとしています。特に、1905年の日露戦争後に浮上した日米共同での満洲開発計画が、外相小村寿太郎の反対で破棄されたことが、対米関係の分岐点となりました。
また、1923年の日英同盟の失効が、両国間の協調を難しくしたことも指摘されています。これらの経緯を通じ、辻田氏は、協調外交が理論上可能であったとしても、当時の日本の状況を鑑みれば現実的ではなかったと述べています。

この記事に基づき、以下のコメントを生成します。
この歴史的な出来事を紐解くと、当時日本が抱えていた外交上のジレンマが浮き彫りになります。しかし重要なのは、歴史の教訓です。まず、国が直面する問題を冷静に分析し、長期的な視点で外交戦略を練る力が欠けていたことがうかがえます。国内世論や外部への不信感が政策決定に影響を与えた点も見逃せません。それはまさに制度の欠陥と言えるでしょう。この反省を活かし、現代では信頼を構築する外交体制を確立すべきです。具体的には、1) 透明性のある外交政策による信頼の醸成、2) 国際的な資源供給の多様化、3) 国内教育を通じた国際理解の深化が挙げられます。
過去の過ちは繰り返さず、未来により良い選択を残すことが、国家の真の強さなのです。
ネットからのコメント
1、歴史にもしはありえない。日露戦争のように初めから戦闘能力を考えて、アメリカの仲介を戦略に入れて戦争に突入した。それでも旅順の要塞の固さや、シベリア鉄道を片道切符でロシア軍を送ってくるとは考えなかった。戦争になれば意外な事が起こる。それでもイギリスと同盟を結んでロシア艦隊を喜望峰廻にさせたり、戦費を調達したり、アメリカの仲介を戦争前から頼んで置いたりと、すべて考慮の上戦争に臨んだ。出たとこ勝負で神様やら大和魂だけで戦えるものではない。
2、異例の3期目を務める強欲なルーズベルトが、日本にサディスティックな要求を突きつけて開戦に追い込んだという説もあり、大戦中の日系人に対する酷い扱いや、チャーチルが止めるのも聞かずソ連の参戦を強く求めたという事実に照らして、それが正しいように思う。
3、当時は、人種差別と欧米諸国によるアジア、アフリカ諸国への植民地という背景がある限り、争い事は避けられなかったと思う。基本今の時代の人種平等の考えがないし、日本人は劣等民族扱いで、例えアメリカとの戦争がなくても、何らかの対立や犠牲は避けられなかったとも考える。
逆にアメリカからの条件を飲んでしまうと、段々と日本の力を削がれてしまって、日本が植民地の方向へ行ってしまう可能性も否定出来ないし、むしろ戦ったからこそアメリカも日本の事を評価し、今の日米同盟や基本人種平等につながったとも考える。アジアやアフリカ諸国が独立出来たのは、戦争による欧米諸国の疲弊だし、よく戦争はいけないややっては駄目だと言われるけれど植民地支配を受け入れて家畜の扱いの方がいいの?という疑問も生まれるし、むしろなるべくして戦争になったとも思うし、ヒトラー自身も目的は違うけれど、結果アジア、アフリカ諸国の独立に力を貸した。
4、問題は、アメリカに戦争を仕掛ける必要があったかどうか、です。宣戦布告をアメリカにはせずに英・蘭のみに宣戦を布告し、フィリピンを素通りして仏印・マレー半島・ジャワ島などの資源地帯を確保したのちに東進するのではなく西進してインド方面を攻略していれば、あるいはインドが占領でき援蒋ルートと英の兵站を断つことができた可能性がありました。アメリカは参戦反対世論が根強く、日本に攻めさせないと直接第二次世界大戦に参戦できないというジレンマを抱えていたことを政府・軍部が共有できていれば、史実とは違った戦略が取れたのではないかと思います。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/03b3f42023d7fe26f17e845353b507474885b383,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















