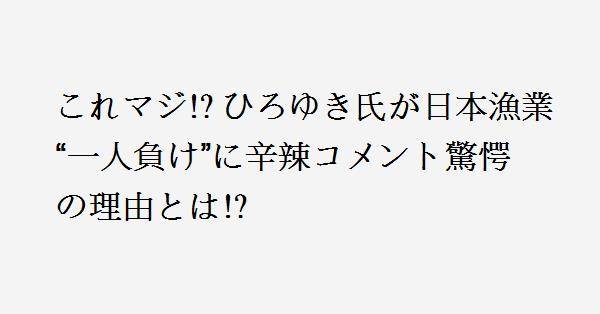
西村博之氏が出演したABEMA「Abema Prime」で、日本の漁業が1984年の漁獲量1282万トンをピークに現在では約3分の1に落ち込んでいる問題が取り上げられました。世界全体では漁獲量が増加しているのに対し、日本だけが減少していることを「一人負け」と表現し、ひろゆき氏は日本人が魚を取り過ぎていると指摘。具体的には、日本は小さな魚でも売るために捕獲する一方で、ノルウェーでは一定サイズ未満の魚を海に戻す措置が取られていることを比較しました。
この現状に対し、ひろゆき氏は過去の「食べて応援」という文化に強烈な皮肉を述べました。

この状況は、日本の漁業における制度の欠陥を露呈しています。漁獲量が大幅に減少し続ける現実は、日本が資源管理に失敗していることを示唆しています。小さな魚も無分別に捕獲される状況は明らかに持続不可能で、漁業資源の保護が急務です。
これを解決するための一つの手段は、ノルウェーのように、成熟した魚だけを確保し未成熟な魚は海に戻す法制化を目指すことです。次に、漁業者へのインセンティブを削減すべきです。収入を補助金などで安定させ、過剰漁獲を抑制する必要があります。さらに、市場に出回る魚のサイズを規制し、消費者の意識を啓発することも重要です。
日本の漁業政策は、持続可能な未来を築くための価値観を再定義する時に来ています。
資源量維持の政策を推進しなければ、日本の漁業はその豊かな歴史を失う危険に直面するでしょう。
ネットからのコメント
1、温暖化海水温変化や中国の密漁(特にイカが多いとの事)もありますが、基本的には日本の漁業者の乱獲が主要因と言う見解は海洋学者の一致した見解です。日本の漁業は他国と事情が異なり強力な保護の下で行われてきました。最たるものが漁協への補助や港湾の税による整備と使用、そして漁業権です。資源保護に強力な規制を求めると同時に中国などの密漁に関する強化も求めます。
2、大手水産会社の大型漁船が小魚からごっそり取ってしまうみたいですね、そして、そーゆー会社に水産庁からたくさん天下っているので、規制も出来ない。シラス取るのも良くないですよね。まあ、こんな中でもブリとかオオズワイガニとか沢山取れているものもあるので、いま取れているものを食べてれば良いし、後は養殖ですよ。今の養殖魚、とくに真鯛なんか凄く美味しくなっていますよね。
3、ノルウェーの件だけど、自分は10年以上前にニュース番組の特集で知りました。そして現在も日本の漁師はガソリン代金払って漁に出れば、やはり手ぶらでは帰れないよね。
しかし、沢山取れたのが小魚サイズではスーパーでも売れ残りだったらやはり取らない方がいいよね。それを解決するのは海洋や陸上での養殖だと思う。燃料使って、獲れる獲れないのギャンブルでは無く、決まった光熱費、人件費から確実に必要最低限な出荷量をコントロール出来る。荒波の海に出るより安全だし。
4、アメリカの漁船は環境保護官が同乗して混獲の調査を行い、外道が多い場合や幼魚が多く水揚げされる場合は漁場を変更させる権限があるのだそうです。日本も漁業に規制を掛けなければ、いずれ獲り尽くしてしまいます。せめて、大型漁船には水産庁ではなく環境庁から監視員を乗せるべきではないでしょうか?
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/d3c11d6bd724f0d48d41cbe19c94e315db16d94a,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















