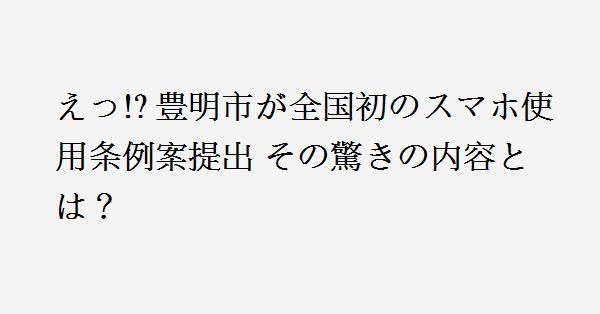
愛知県豊明市は、市民が余暇の際にスマートフォンやタブレット端末を1日2時間以内で利用することを目安とした条例案を提出した。この条例は強制力や罰則を伴わず、施行は10月1日からである。条例案には全国初の試みとして、スマートフォンの使用時間を明記している。市の関係者によれば、子どもがスマホに依存し過剰に利用するケースや、親が乳幼児に長時間スマホを使用させる状況を把握しており、福祉施策の一環としてこの対策を検討した結果、条例制定に至った。
さらに、睡眠時間の確保を目的に、小学生のスマホ使用は午後9時まで、中学生以上は午後10時までとすることを推奨する内容も含まれている。
スマートフォンの過剰使用は、現代社会で急速に拡大する問題です。豊明市の条例案は、一見市民の健康を守る利点があるように思えますが、実際には根本的な問題解決を見逃している可能性があります。まず、強制力や罰則のない条例であるため、効果の実証が困難です。また、基準が曖昧であることから、実際にどれだけの市民が遵守するか不明です。次に、この取り組みが教育や啓蒙活動を通じて市民の意識向上を促す方策を欠いているのが問題です。具体的な改善策として、地域の学校やコミュニティセンターでの啓蒙活動、スマートフォン使用に関する教育プログラムの実施、そして市民に対する健康意識向上キャンペーンの展開が考えられます。これらの取り組みが一体となることで、技術依存の危険性を真に理解し、適正使用の意識が市民に浸透するのではないでしょうか。豊明市が掲げる未来像には、単なる法規制ではなく、充実した教育と社会参加による意識改革が求められています。
ネットからのコメント
1、香川県のゲーム条例もそうだが、地方議会が無法地帯のようになっていて、さまざまなシチュエーションなどをたいして考えないままに適当に思いついたかのような条例が通ってしまう。たんなる努力目標だからといって容認せずに、こういう地方議会の横暴にはきちんと声を上げてゆくことが重要。
2、「SNSの使用はー」とかならともかく、様々な用途があるスマホそのものの時間規制なんて、すでに時代に取り残されてる老〇の発想と断じて差し支えない。こういうのが行政の決定機関にいまだにはびこっていることが日本を停滞させている一番の原因だと思う。
3、「2時間」という制限の根拠が極めて曖昧。市が挙げるのは一部の子どもの依存傾向や育児における使用事例だが、それは個別の家庭で対応すべき問題であり、全市民に一律の「目安」を押し付ける理由にはならない。科学的な裏付けもなく、感覚的な不安に基づいた政策でしかない。現代社会において、スマートデバイスは情報収集、学習、創作、交流など多岐にわたる用途を持つ。これを「仕事・勉強以外は2時間まで」と制限することは、市民の創造性や自己表現の自由を抑圧する行為だ。
条例案は「家庭でのルール作りを推奨する」としているが、市民の生活に対して「こうあるべき」という価値観を押し付けることは、自治体の役割を逸脱している。本当に市民のことを思うのであれば、まずは教育や啓発を通じて自律的な判断力を育てるべきであり、行政が「時間制限」という安易な手段に逃げるべきではない。
4、地方議員も国会議員も資質に欠ける議員が多い。裏金、パワハラ、セクハラ、贈収賄、議会中居眠りなど不祥事議員が多すぎる。地方も国も無駄に議員が多すぎて経費がかかりすぎる。これらの経費は国民の血税から捻出されている。 人口減少の折に議員の定数が変わらないのは道理に合わない。地方も国も身を切る改革をして議員の定員削減してまともな政治をして欲しい。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/f166e221aad0fcba68fac94761a26ef2ea3bf064,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















