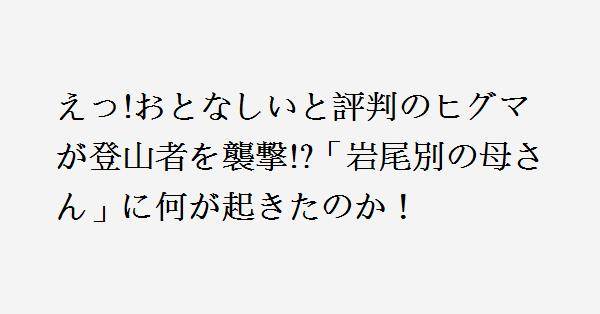
8月14日、北海道斜里町の羅臼岳登山道付近で男性がヒグマに襲われ、翌15日に遺体で発見される事故が発生しました。襲撃に関わったヒグマ3頭は駆除され、そのうちの1頭、通称『岩尾別の母さん』がDNA鑑定で犯行個体と判明。大人しいと評判だったこのヒグマは、最近の出産で神経質になっていた可能性が指摘されています。また、人間がヒグマに近付きすぎる行動も一因とされます。
事故現場はヒグマの餌場としても知られる「ヒヤリハット地点」でしたが、効果的な注意喚起が不足していたことが問題として浮上しています。現在、羅臼岳は入山規制中であり、さらなる事故防止策が求められています。

事件批判
今回の事故はヒグマとの距離感を軽視し続けた人間社会の落ち度が招いたと言わざるを得ません。ヒグマに「問題行動がない」との認識が甘すぎたこと、また、撮影目的で無闇に近づく人間が熊を人慣れさせる要因となりました。さらに、事故現場が「危険箇所」として以前から指摘されていたにもかかわらず、訪問者への十分な危機意識を植え付けられなかった点も異常です。看板だけでなく、国や自治体が本格的な対策を怠ったツケが今回の結果ではないかと疑われます。
問題の本質
この事件の背景には、「自然と人間の境界管理」の失敗があります。
熊に近寄る軽率な行動、規制不足、そして熊が人間を恐れなくなった環境作り—何れも長年の課題の蓄積です。また、観光地としての魅力と自然環境の安全性向上がバランスを欠いていたことも露呈しています。
解決策
厳格な距離規制の導入と罰則適用:ヒグマとの距離を守らせるため、登山者やカメラマンへの教育と同時に違反者への厳しい罰則を設ける。
技術支援の強化:危険エリアを示すアプリや地図、ドローンを使った熊の位置情報共有など、テクノロジーを活用した予防策を展開する。
地域主導の安全教育:地元の案内人やガイドによる具体的で分かりやすい安全講習を義務化し、熊と共存する価値観の共有を促す。
強烈な結びつけ
人より熊が危険なのではなく、熊より人の無自覚が危険なのです。冒険心が自然への敬意を凌駕する時、本来避けられる惨劇が生まれてしまいます。この教訓を無駄にせず、人間が自然との距離を正しく知る場とすべきです。熊にも人にも次はありません。
ネットからのコメント
1、そう思いたいのはわかるがサファリパークや、動物園でも長年世話した動物に襲われ、亡くなった飼育員も複数いる北海道だけでも、長年飼ったヒグマに襲われた亡くなった事故もある慣れた故の認識の緩みは無かったか?と思います知床のヒグマは優しいと言うのは、訪れた観光客に誤解させないか危惧します野生動物は、いつスイッチが入るかわかりませんよね
2、地元の方からしたら愛着のあるクマなんだろうけど、『人との距離感が近すぎる』のであれば、いずれこういう事故につながったと思う。飼いならされた犬でさえ、体調や環境の変化で飼い主が思いもよらないこどするんだから、クマなんか何をしたって不思議じゃない。そう思っていることがクマにとって殺処分を免れる一番親切な気持ちだと思う。写真を撮る、餌付けをする、近寄って行く、これらが今回の事故の前提としてあったとして、『人を恐れるように積極的に学習させなかった』こともまた前提条件なのではないだろうか。
3、岩尾別の母さんと呼ばれていた、メス熊は、久しぶりに子熊を産み育てている熊だったと言われています。ヒグマや野生動物たちと人との境界線を人が壊して、静かに母子で暮らしていたのに、そのメス熊を餌付けしていたと聞きました。人の食べ物は、とてもカロリーが高くヒグマや野生動物や野鳥たちは、執着してしまいます。優しく親しげに餌付けする人達と食べ物の味を覚えると狂ってしまいます。それに、メガソーラーなど大自然の破壊をヒグマや野生動物や野鳥たちは、とても敏感です。
ヒグマや野生動物や野鳥たちは、人に出会いたくなくて隠れているのに、隠れ場所や住みかや虫や蟻などのその時期に必要な食糧を人達が荒らしています。改めて、ヒグマや野生動物たちと、人里との境界線が必要です。人の食べ物を知った熊は、人を襲います。そうなると、人は命を落とすか一生の傷となるし、ヒグマたちも処分されています、処分されてしまいます。
4、今後の被害を考えると、致し方ない決断なのだと思います。遠くで生活している人が口を出して良い問題ではない。動物園とは訳が違う、檻がない場所でどうやって人肉を覚えたクマから駆除せずに身を守るのでしょう。そこは人をファーストに考えて良いのだと思います。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/2aa2e5adfcb819abe5f71154dfeebb0b1793f92c,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















