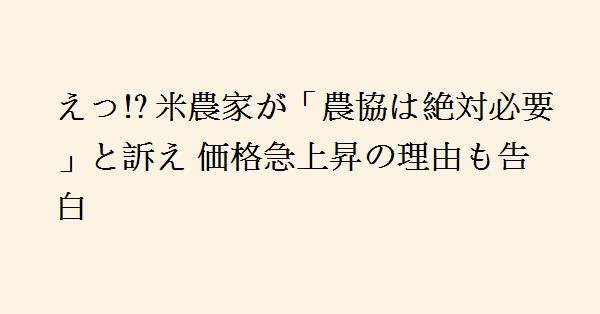
2025年8月21日、JA(農協)の存続をめぐり、小泉進次郎農水相と農業関係者の議論が報じられました。小泉氏は「農家がJAを選ぶか選ばないかは自由」と述べたのに対し、京都府京田辺市の米農家である松井雅彦さんは「JAは絶対必要だ」と反論。松井氏は、農協が農業指導や相談窓口として機能し、地域農業への寄与が大きいと強調しました。
また、新米の価格に関して、令和5年以降の高温障害や害虫被害により収穫量が減少、白米の供給不足が進んでいることから、今後も米価が上昇するとの見解を示しました。現在、JAの60キロ当たりの概算金は高騰しており、消費者負担増が予測されています。

農業の根幹を揺るがす現状には重大な問題が隠されています。小泉農水相は、JAの存続問題について「選択の自由」と表明しましたが、この発言は一見すると多様性を促しているように見え、その実、農業基盤の弱体化を黙認する立場とも取れます。現場の農家が直接声を上げるほど、JAが果たしている実務的な重要性は明白であり、単なる自由競争に任せれば、長期的には農業の存続そのものが危ぶまれる可能性が高まるでしょう。

制度的欠陥は、農業政策の現実性の欠如にあるといえます。第一に、JAを通じた農家支援を維持しつつ、効率化を進める形での改善策が求められます。次に、環境変化に適応する具体的な支援を国が明確化し、農協との共同プログラムを整備すべきです。さらに、急増する米価高騰に対処するため、安定的な価格政策と備蓄対策を早急に打ち出す必要があります。

農業は個人の選択に委ねられる単純な市場メカニズムでは支えきれません。国家全体の食料安全保障や地域経済の基盤を支える課題として、農政の再構築を強く望むべきです。農業の未来を「自由」の名の下に崩壊させることがないよう、鋭い目を光らせ続ける必要があります。
ネットからのコメント
1、学校給食用のみJAさんへ出荷しています。農協さんは、概算金と経費を引いた追加払いを明細で知らせてくれます。
そして、記事の通り地域の栽培指導と病気や害虫発生時の対策などもしてくれています。組合員以外の方々に農協を議論して欲しくない、という意見が多いです。
2、自分は水稲農家だけど、JAには出荷していません。でもJAがいらないかと言えば、そうではないと思う。自分にとっては殆どお世話になることはないけど、新規で就農する人や多くの人と繋がりを持ちたい人には、青壮年部活動とかJA指導員との繋がりは大事になってくる。良い部分も悪い部分もあるので、改善は無理かもしれないが、生暖かい目で見ていく気ぐらいはあるよ。
3、JAの役割を軽視する意見がありますが、現場を知らない議論だと思います。大規模農家なら自前で倉庫や販路を持つこともありますが、多くの農家はそこまで手が回りません。そのため、痒いところに手が届くJAの存在は必要不可欠です。本来、協同組合とはそうしたサポートのためにあります。「JAはいらない」という主張は、農業の現実を知らずに語っているように感じます。また、小泉氏のパフォーマンスだけの政治を持ち上げる風潮にも違和感があります。
風評を撒き散らし、国を混乱に巻き込んだ以上、自ら責任を取って辞任すべきでしょう。まずは現場を知り、実際にやってから意見を述べるのが筋だと思います。
4、農家のための農協であるべきという大臣の発言は正論。では農家のための農協でない農協とはどういう農協か。自分だけで高く売り抜けたい農家は農協を批判するけれども、そういう農家までのための農協であるべきか。農協は出来るだけ多くの農家を取りこぼさない農協を目指していると思う。一匹狼は致し方ない。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/4c36404c5a0105200f96ec2925aadce1570a3e5d,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















