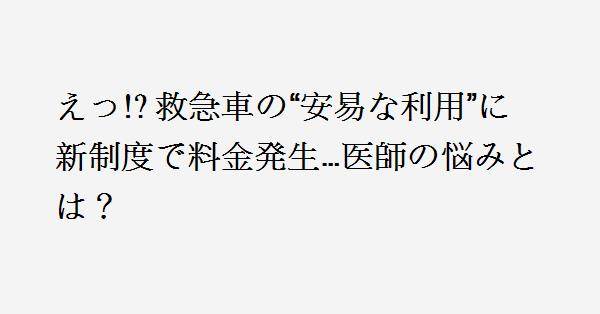
【事件概要】
2024年12月より茨城県、同年6月からは三重県松阪市にて、緊急性の低い救急搬送に対して「選定療養費」の徴収が始まりました。筑波記念病院では年間6000件超の搬送を受け入れており、ある16歳男子高校生が頭部を打撲して2時間後に救急車で搬送され、CT検査で異常がないと判断されました。その結果、「緊急性なし」として7700円の選定療養費が請求されました。
別の事例では、熱性けいれんで泡を吹いた1歳児の母親が、医師や相談窓口の指示で救急搬送を依頼したにも関わらず、緊急性なしとされ同様に費用を徴収されました。導入後、軽症の救急搬送は減少した一方、患者の納得感や医師の判断負担に課題が残されています。

医療費の抑制という名目のもと、「緊急性がなかった」という結果論で7700円の負担を市民に求める制度が始まっている。問題は、症状が落ち着いたかどうかではなく、搬送を要請した当時の“切迫感”にある。それを無視して事後評価だけで金を取るなら、自己判断で救急車を呼ぶことを萎縮させ、命に関わる事例を見逃す土壌をつくる。
制度の欠陥は3つ。①緊急性の定義が曖昧で、現場の医師の裁量に全てを委ねていること。②症状が落ち着いた場合でも一律で費用が発生する点。③小児や高齢者など判断が難しい層への配慮が欠如していること。
改善策として、①緊急性判断のための第三者機関の設置、②症状発生時の証言や相談履歴を根拠に免除対象とする制度、③小児・高齢者・障害者などに対する柔軟な免除規定の導入を提案したい。
「命を守る行動」にペナルティを課す制度は、医療の本質を見失わせる。病気は診断結果ではなく、不安と危機感から始まるのだ。その感情に冷水を浴びせるような制度で、本当に健康な社会と言えるだろうか。
ネットからのコメント
1、こういう問題が出てくるなら、全部一律で徴収したらいい。そもそも病院での診察は治療費かかるし、命を助けてもらうのに7000円くらい安いと思う。生活困窮者は救急車を呼べないとか言う人いるけど、今でも治療費が払えない人のために行政が肩代わりする制度がある。生活保護受給者の多くが救急車を頻回利用している事も報道して欲しい。
2、救急車を呼んだ場合は有料で良いと思います。近所の大きな総合病院で紹介状なしの初診料が1080円の時は元気な高齢者の集いの場のようになっていていつも混雑しており、診察を受けるのに随分時間がかかりました。それが5500円になった途端、不要不急の方が来院しなくなり、混雑も緩和しました。
個人的な意見ですが、全員有料になれば、無料のタクシー代わりに利用したり、自分で通院出来るのに取りあえず救急車を呼んだりする人等は減るのではないでしょうか?
3、物品も薬剤費もあがっていて、医師看護師は給与ほぼあがっていないが、事務方や掃除の方などの給与はあがっており現在医療が維持出来なくなっている。維持するための方策として、救急車有料化、高額療養費増額、OTC薬有料化、保険料増額、医療レベル低下があるが、全て嫌は通用しない。諦めるしかないと思う。
4、救急車を呼んだときは、患者の容体が良くなくても、少し時間が経ったら、良くなることはある。それでもいいじゃないか。命が助かるのなら。7700円は高いかもしれないが、もしということを考えたら救急車を呼んだ方がいいし、それで少し回復したのならそれはそれでよかったはず。選定療養費が高すぎる・・・なんて、無事だったから言えること。「納得できない」なら、最初からタクシーでいいじゃないか。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/2f90c76bea872a88c216a05136f97127cfae5e12,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















