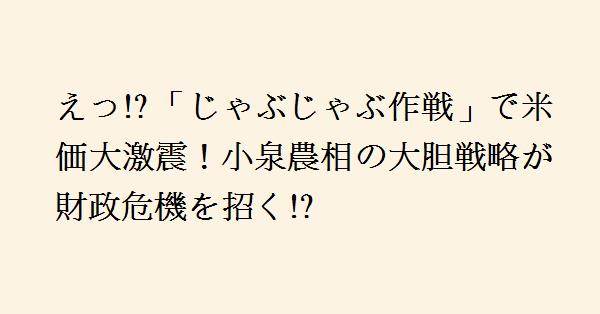
小泉進次郎農林水産大臣による「じゃぶじゃぶ作戦」が原因で市場に影響が出ている。2023年5月下旬、小泉氏は備蓄米を市場に放出し、米価を下げようと試み、実際、首都圏のスーパーでの米価格は6月以降下がった。この政策は短期的には消費者の恩恵となっているが、生産者米価は依然として高い水準を維持し、JA阿蘇では前年より約8,220円高い過去最高額の3万240円が提示されている。
安価な備蓄米の放出により農家の経営への影響が懸念されている中、農政の価格介入が長期的な財政赤字を生む可能性に批判が向けられている。

小泉進次郎農相の「じゃぶじゃぶ作戦」は、日本の米市場に予期せぬ結果をもたらした。備蓄米の価格介入による一時的な小泉支持も、実際には深刻な問題を隠蔽している。農家は利益を生み出す代わりに、税金を使って市場に放出された備蓄米で打撃を受けている。このような介入は、過去の借金地獄を再現する恐れがある。まず、農家の生計を維持するための価格安定策を見直し、価格形成は市場に任せるべきであり、政府による急な介入を避けるべきです。また、低所得層に対しては米の無償配布といった直接支援を検討するのが有効でしょう。これらは、持続可能な農業と市場の健全な競争に寄与するはずです。税金を消費しつつ市場を操作することは、過去に我々が経験したとおり、長期的に国家の財政に悪影響を与え得ます。
経済のダイナミズムは自然な流れに沿うべきであり、小手先の介入ではなく、より構造的な政策が必要とされる時期です。
ネットからのコメント
1、>「民間の価格の上下に任せるべきだったんじゃないか。どうしても生活が苦しくコメを買えないという人がいるのであれば、低所得者への備蓄米の無償配布などをするべきでした」その民間に任せきりにしていたのを猛烈に批判したのが国民でしたから、政府も手を付けざるを得なかったのでしょう。それにお米を無料配布しても、メルカリで転売する人が大量発生するだけだと思う。お米の値段が高ければ、それをする価値は更に上がるでしょうし。でも、一番の問題はお米の高止まりが続き、消費者の米離れが加速する事では。そうなると、一番困るのは農家だと思うけど。
2、日本の米農家の95%は10ha未満の水田の小規模農家です。農業の生産は太陽光の降り注ぐ面積を超えて収量は増えませんから、一家の生活を賄うにはある程度以上の面積が必要です。政府は米農家の基準を決めて、それ以上の規模の経営体を目標とすべきです。それ以下には所得補償はせず、耕作放棄地には適切な固定資産税をかけ、大規模、集約化に協力して田んぼを農地バンクに預けるか売るか交換する農家と、自ら買うか借りるかして大規模農家を目指す農家両方に補助金を出して、どちらも損しない制度にして、基準を超えた経営体には補助金を縮小できます。
中山間地で、大規模化が物理的に不可能でも、景観や防災などのために田んぼにすべき地区は別の概念の補助制度で守るのです。とにかく、”将来の補助金総額減額を目指して、農家を守るから農地と収穫量を守る”への転換が必要です。
3、少量の米を作っていますが、農機具が故障すればおそらく継続はできません。周りの小さな米農家さんも次々と後継者がいなくなったり、農機具の故障で廃業し、農地が荒地に変わってきています。米農家が今の価格でも生きられるのは大規模な土地を持って作っている人だけです。備蓄米は結果的に税金の負担で安くなっているだけで、これにより税金をさらに上げられれば元も子もないですね。高い農機具に補助をつけて小さな米農家を守り、量産させて、米価を下げれれば一番の理想とは思います。
4、冷夏でもなかった去年。なぜ急に米不足になったのか?根本原因が解決されたのか?そして今年は猛暑で本当の米不足になりそう。備蓄米ないのに、どうするんでしょう。食用もですが、加工・飼料用…スンズローさんのフットワークが軽いの評価してますが、自民自体が政治集団としと無策すぎる。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/72dd2d2eff6b8e0023ff8348595da497bad087a3,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















