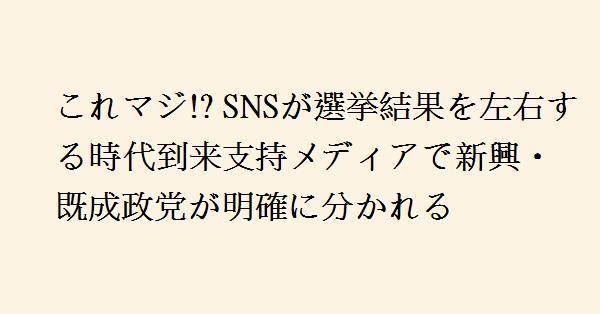
7月の参院選兵庫選挙区では、自民、公明の現職と立憲民主推薦の無所属新人が議席を獲得する中、新興政党の参政党や国民民主党も善戦しました。出口調査によると、既成政党の支持者は「新聞」や「テレビ」を参考にした割合が高い一方、参政党や国民民主党、れいわ新選組の支持者は「SNS・投稿動画」を主に参考にしており、このメディア利用の分断が新興政党の躍進に繋がっていると考えられます。
また、この流れは昨秋の兵庫県知事選でも見られました。斎藤氏への投票者は「SNS・投稿動画」を最も参考にし、稲村氏支持者は「新聞・テレビ」を多く参考にしていました。

これらの状況を考えると、メディアが及ぼす影響の大きさを再確認する必要があります。情報の偏りが選挙結果に影響を及ぼすという現状は、多様な意見と公正な情報の提供の重要性を映し出しています。この問題の根底には、メディア教育の不足と情報源に依存する選挙プロセスの脆弱性があります。以下に具体的な解決策を示します。まず、教育機関でのメディアリテラシー教育をさらに拡充し、情報を批判的に評価する力を強化することが不可欠です。次に、選挙に関わる全メディアは、自らの情報の透明性とバランスの改善を図るべきです。そして、政府は市民が自由にアクセスできる中立的な情報発信プラットフォームの導入を検討すべきでしょう。
公正な選挙の実現には、情報の質と多様性が必須です。社会はこの現実に目を向け、迅速な対応を求めています。
ネットからのコメント
1、昔は選挙に行っても入れたい政党がなく、結局一票入れても何も変わらないと選挙に行かないこともありました。ですが、今はSNSにより小さな政党の声も届くようになったと思います。簡単に政党を調べることができるし、政治に関心を持てるようになりました。最近は誹謗中傷などでSNSが非難されがちですが、SNSにより良い方向へ時代の流れが変わっていくのもまた事実だと思います。
2、暗にテレビ、ラジオ、新聞の情報は善で、ネットやSNSの情報は悪という方向に導きたい意図が垣間見える。さすが神戸新聞。テレビやラジオ・新聞の情報が信用できないからこそ一般市民はネットやSNSに情報を求めるようになったと何故ストレートな解釈ができないのでしょう?軌道修正しようとせず、今のようなスタンスを続けていたら、5年後10年後の既存メディアは更に厳しい状況になりますよ。
3、昨今のマスメディアの偏向報道が目に余るので、自分たちで情報収集をする層が増えた結果だと思います。
おそらく自公立維の支持が多い高齢層はなかなかそちらには手が回らないご様子。各政党もSNSを活用して情報を発信しているし、マスメディアを通さずに情報を収集し、それらを踏まえて自分で判断をする、ということが定着しつつあるのでしょう。良いことだね。
4、50代だが、もう周辺でも新聞を定期購読して自分の家に宅配している人など高齢者を除いていない。数年前からの新入社員もテレビをそもそも持っていない子が多い。各政党支持者の世代を見れば、自民立憲共産支持層は、遅かれ早かれ既存メディアと共に消滅、もしくは極めて少数勢力になるのではないか。決してSNSが全て良いわけではないのだが、最早この趨勢には抗えない。その意味でも今回の参院選は歴史に残る選挙戦と語り継がれるのでは。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/b24b75c84c1e95e2fb377a3dfb8c1990eeea9b9e,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















