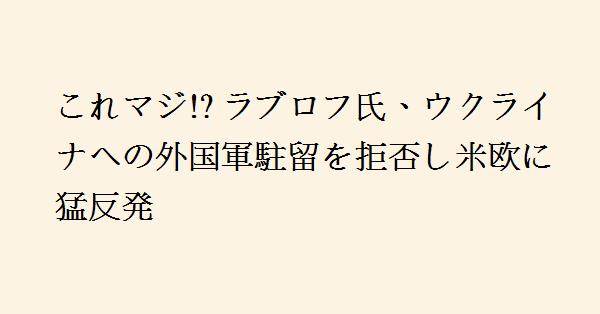
事件概要:ロシアのラブロフ外相は、ウクライナの安全保障に関する議論に対して、ロシアが関与しない形では解決できないと主張し、米欧による「安全の保証」検討を強く牽制した。また、ウクライナへの外国軍の駐留を「許容しがたい」とし、対立的な姿勢を明確にした。一方で2022年春のトルコ・イスタンブールでの和平協議では、ウクライナが提案した多国間安全保障枠組みに賛意を示していたと主張。
現在、米欧諸国はNATO第5条に類似した集団的安全保障モデルを検討中で、ロシア側の拒否権を条件とする構想も浮上しているが、ラブロフ氏は欧米主導の一方的発議には展望がないと断言。和平協議の行方は難航が予測される。

コメント:ロシア外相がウクライナの安全保障問題で再び排他的な態度を示したことは、国際的な和平プロセスの重大な停滞を象徴しています。この態度は、集団的安全保障の枠組みを拒絶しながら、ロシアの拒否権を執拗に求めるという矛盾によって問題の根本を露呈しています。こうした姿勢は結果的にウクライナの国家主権や防衛権を奪い、多国間調停そのものを弱体化させかねません。背景には、ロシアが国際秩序を自身の利益の枠内でのみ再構築しようとする長期的戦略があるといえます。
解決策として、まず関係国はロシア以外の安保枠組みをより具体的に形成し、ロシアの不参加が及ぼす影響を最小化する戦略を練るべきです。
次に、紛争地への外国軍駐留に関し、地域的安定化に必要な国際監視団の設置を検討する必要があります。また、国連などを通じた、中立的な調停機関の強化を図り、拒否権に基づく停滞を防ぐ制度設計も急務です。国際社会が団結し、このような理不尽な状況に対抗することが、文明間の価値観を守るために必要不可欠です。今問われているのは、共存を目指した国際秩序の実効性であり、これを無視する限り平和実現は遥かに遠い未来となるでしょう。
ネットからのコメント
1、この発言を見てもロシアはウクライナ全土を征服する意図があることが分かる。沖縄の米軍とウクライナへの外国軍駐留を同じに見ている意見があるが状況が全く違う。ウクライナには欧米の軍隊が期間限定でも駐留すべき。そうでなければ「安全の確保」ができない。
2、トランプ大統領はもともとロシアが8/8までに停戦に応じなければ制裁すると言っていたはずだ。アメリカとロシア、ウクライナそれぞれとの首脳会談ののち結果的にロシアは停戦するつもりもウクライナとの直接対話をするつもりも全くないことが分かったと思う。
アラスカでどんなディールがあってトランプ大統領のスタンスが豹変したのか分からないが、ロシアと話すたびにコロコロと態度が変わることに強い違和感がある。
3、国内経済も崩壊し、1ヶ月で終わると言われていた戦争に3年以上費やし、ロシア兵も何十万人と失い本当に戦争を辞めたいのはロシアの筈。もちろんウクライナに自国だけで戦える力は無く西側の支援疲れによるウクライナの領土割譲で手を打てと言う西側の無言の圧力と言う状況をロシアは十分に理解し強気な交渉術と言った所でしょう。
4、最近、プーチンの言動は控えめだが、このラブロフやメドヴェージェフのそれは過激になってますね。中国と同様、国内向けと国外向けで言葉と立場を使い分けているのだと思います。弱い政府をロシア国民に見せたくない以上、手下の口上は威勢がよくなるのは致し方ないところ。ロシアの戦時経済は個人消費が振るわなくなり、友邦のロシア離れもあり、立場は苦しくなりつつありますから、同国の本音は「できる限り勝った形で戦争を終わらせたい」になっていると思います。毎日も字面だけ追わずにもっと掘り下げたロシアの真相を探るべきだと思います。
ソ連が崩壊した時、日本のマスメディアはどこもそれを予想できずにただただ驚愕しただけでしたが、今回も同じことを繰り返すのでしょうか。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/1741ca460533e975dd904492ef3fc861a9377dde,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















