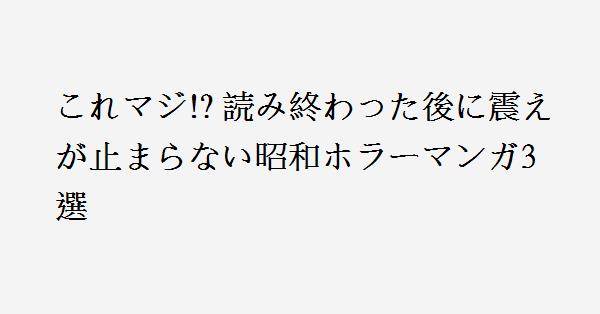
事件概要:
1970年代から1990年代にかけて、多くのホラーマンガが日本で誕生し、読者に衝撃を与えてきた。中でも日野日出志氏の『蔵六の奇病』では迫害と奇病に苦しみながら美しい絵を描き続けた主人公の悲劇、また高橋葉介氏の『腸詰工場の少女』では貧しさと極悪非道な人間に翻弄された少女の悲惨な結末が描かれた。
さらに楳図かずお氏の『洗礼』では親の異常な愛情により精神を歪められた少女の悲劇が提示されている。これらの作品はいずれも社会的問題や人間の闇を背景にした救いのない結末で、人間の内面的な恐怖を表現している。

コメント:
人間の醜さや社会の理不尽さを描いたこれらの昭和ホラーマンガ作品は、単なる娯楽以上に深いメッセージを含んでいる。『蔵六の奇病』に見られるような孤立と迫害、『腸詰工場の少女』で繰り返される弱者搾取、『洗礼』が示す毒親の影響は、それぞれが現実に存在する問題であり、普遍的で解決すべき課題だ。特に、救いのない結末が際立つ理由は、単に物語の悲惨さに留まらず、人間社会の不平等や虐げられる個々の苦しみを浮き彫りにするからである。
これらの作品から学べることは、悲劇が生まれる土壌そのものを変えなければならないという現代の課題だろう。例えば、弱者への配慮を拡大させる社会制度の構築、教育を通じた倫理観の強化、そして偏見や差別を助長する文化への批判的アプローチが実行されるべきだ。人間同士の心なき無関心が、ホラーの中の世界だけでなく現実でも悲劇を招く。これが幻想の物語で終わらない現実の再現であるなら、我々は常に自問し続ける必要がある。人間性とはどこにあるのか、と。
ネットからのコメント
1、マンガのホラーは読み漁ってもいないが、有名なものだけに紹介された作品はたまたま全部、既読だった。ホラーはSFやミステリーと違って自由度が高い分、返ってネタバレしやすいんだよね。斬新な展開というのはあまりない。お約束の展開でも楽しめるのも、恐怖というテーマと画力による「ホラーマンガ」の特徴かもしれない。
2、35年程前の夏休み親の実家に行った際、2階の部屋に楳図かずおの洗礼がありました。おそらく母か叔父が昔残していった物だと思うけど。当時小一になるかどうかの私はそれを読んでしまい、トラウマで夜眠れなくなった記憶があります。
つい先日なぜだかまた読みたくなり、配信で探して読みましたが。大人になってから読めば、なぁんだこんな感じのもので夜も眠れなかったのかかわいいな(笑)となるかな、と思って改めて読んだのに、とんでもないですね。今読んでもガッチガチに怖い。というかこんなものを当時小一だかの子どもしかも女の子に読ませたらダメだろと今の感覚では思ってしまうほどの恐ろしさ。というか私が勝手に読んだのだけれど、よく最後まで読めたな私というのにも驚きました。息子が今それくらいの年ですが、おそらく読めないでしょうし、恐ろしすぎて読ませられません。えげつないです(褒めてます)
3、ホラー要素よりも人間ドラマ要素が強いかもしれないが、楳図かずおさんだと鬼姫も名作だった。美しいが残酷な鬼姫の影武者になる事を強いられた貧しい農家の娘である主人公が、鬼姫になりかわるも、やがては全てを失ってしまう切ない話だった。紙ベースの本がボロボロなので、電子書籍化を期待している。
4、エコエコアザラクとか小学校低学年の頃に読んで怖かったな。 楳図かずお先生やつのだじろう先生の作品とか流行っていたと思うけど、父の海外赴任で日本に居なかったから読む機会が無かった。
昭和の漫画や劇画作品はハッピーエンドより救われない結末の作品の方が多かったね。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/99e3c9b0499e54f110a0ee9bcfb87d72f312e2ea,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















