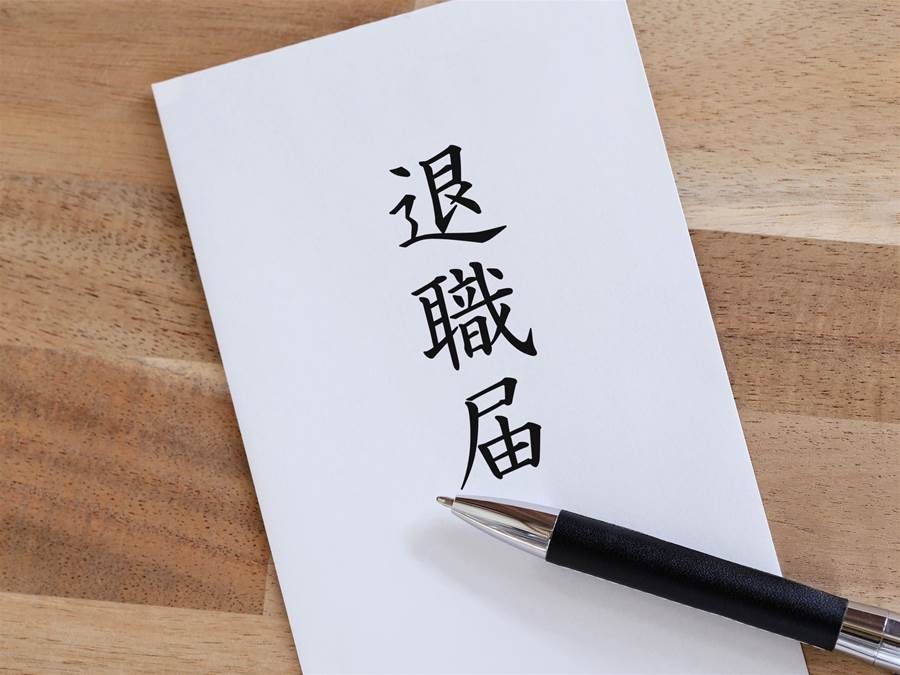
事件概要
2025年1月から7月にかけて、従業員の退職が直接的または間接的な原因となり倒産に至った企業が74件に上った。前年同期の46件から28件増加し、増加率は約60%に達している。もしこのペースが続けば、年間100件を超える見込みで、これは集計可能な2013年以降で最多となる。
特にサービス業や建設業が多く、IT業界や映像制作業界でも目立った。例えば、ピーシーネット(2025年1月破産)はエンジニアの流出が原因で収益性が低下、クレセントホーム(佐賀、2025年5月破産)は幹部社員の退職により営業力が失われた。従業員の待遇改善が進まないことで、賃上げ難倒産も増加しており、今後もこのトレンドは続く可能性が高い。

コメント
企業の倒産が従業員の退職によって加速する現象は、単なる人手不足では片付けられない根深い問題を浮き彫りにしています。特に中小企業で顕著なのは、待遇改善ができない状況が、結果として企業の存続に関わる致命的なリスクを生んでいることです。労働市場が逼迫し、適切な報酬を提供できない企業が淘汰される時代が現実となりつつあります。

制度的には、企業の成長を支える人材の確保に対する戦略が欠如しており、労働市場の構造的問題が企業経営に深刻な影響を与えています。根本的な解決策としては、まず労働環境の見直し、特に賃金水準と待遇の改善が最優先です。次に、企業の人材定着を支えるために、柔軟な労働条件やキャリアパスの充実を図る必要があります。そして、労働者の流動性を抑えるための福利厚生や仕事の充実感を高める施策が求められます。
企業の持続可能性と競争力を高めるためには、人材の流出を防ぐだけでなく、適切な待遇と働きがいを提供することが不可欠です。
ネットからのコメント
1、これまでは詰まるところ誰かの犠牲•不幸の上に世の中が成り立っていたのかもしれません。そんなのイヤだ、皆んなには幸せになってもらいたいという優しさに目覚めたんです。
よってこれからは犠牲も不幸も押し付けな世の中になります。ただ、少し不便にはなります。なんせ誰かがやらなきゃ回らなかったのが、誰もやらないから回らなくなるんですから。でも、誰かを犠牲や不幸から守れるならばそんな不便は軽微なり。と、言える社会にこれからはなっていかざるを得ないのですよ。
2、10年以上前から、日本は中小企業が市場規模に対して多過ぎて、いずれこういうことが起きると予想していたが、当時はそういうことをコメントすると中小企業の社長連中から叩かれたもんだ。だが、よくよく考えてみて欲しい。皆が皆、金持ちになりたい(裕福に暮らしたい)中で、凄まじい数の下請けがいて、社長連中が自分の取り分を取っていって最終的な末端の従業員の給与はいくらになるよ?と考えると、雇われ人としては、そりゃ大企業で雇われた方が絶対、安定化して暮らせるんだわ。地元の中小企業に雇ってもらったところで、末端価格の給与しか貰えずボーナスも無ければ昇給すらしないのだ。給与が上げられないと中小企業社長は言うが、ならば合併なり買収なりして事業規模を拡大するしか方法がないにも関わらず、目の前の仕事ばかりしていちゃ、そりゃ従業員は辞めていくし倒産するわなと。
分かってた懸念が現実化してるだけだ。
3、この炎天下の連日の猛暑日の中、さすがに計算の苦手な若者だって日給月給制の建設業の屋外作業に従事を続けるはワリに合わないと気付き始めたのもあるだろうね。気候や寒暖の差の影響を受ける産業は今度、月給制にして行かないと人材の確保は困難になるだろう。
4、これからはこういった「スタイル」での「倒産」が続出するのだろう。だいいち人口が減少している。一昨年末の「利用客数低迷」ではなく、「運転士減少」が理由での大阪のバス会社廃業は、まさにその予告だろう。今のまだまだ数多い中小零細企業の社長や技術者といった「職人」の多くが、技術継承も出来ないまま引退を余儀なくされ、そしてやがてこの世を「卒業」する頃には冒頭で述べた人口減少の事情も関連して、生活インフラの維持管理が難しくなり、道路関係や老朽化した橋やトンネルのメンテナンスもままならず、当然ながら鉄道やバスの減便や最悪は廃止も免れないだろう。それ以前に否応なしに集落消滅や廃村があちこちで起こるだろうが。いやもっと身近なトイレでも昨今の高機能化も手伝って、万が一故障や使用不能になれば修理完了までに月単位でかかる可能性もあり、都市部でもうかうか出来ないだろう。
これからどうなることやら。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/4dd175527edda8d45d75cda2c26152058d03cfe2,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















