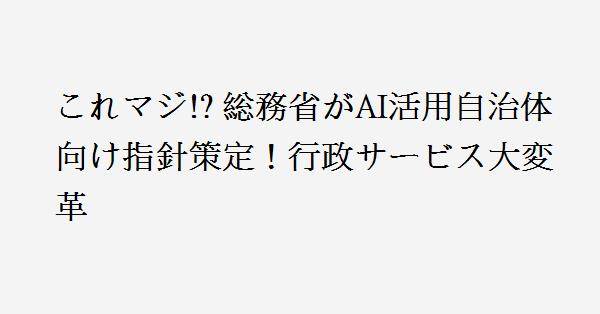
総務省は、全国の自治体に生成AIの具体的な活用法を示す指針を年内に策定する予定だ。深刻な職員不足の中で行政サービスを維持・向上させるため、AIによる業務効率化が求められている。生成AIは、議事録作成や住民相談対応などで既に一部自治体で利用されており、さらなる活用が期待される。だが、生成AIの利用には誤情報や個人情報漏洩のリスクが伴うため、管理責任者の設定や機密情報をAIに学習させない仕組みの構築が必要だ。

生成AIの自治体活用は、制度の欠陥と効果的な管理の重要性を示す。まず、生成AIを利用することで業務効率化が可能である点を強調しつつ、職員不足やベテラン退職によるノウハウ欠如の問題を明確に指摘するべきだ。そして、生成AI導入のリスク管理を怠ると、個人情報漏洩や誤情報の発信につながり、住民の信頼を失う恐れがあるため、具体的な対策が必要だ。まず、管理責任者の配置を標準化し、情報セキュリティ専門の研修を義務付けることが考えられる。次に、AIシステムの調達時に情報漏洩防止策の明記を義務化すること。このような制度の強化により、安全で効率的な行政が可能となる。生成AI活用は、ただの技術進歩以上に、民との信頼構築が重要である。
ネットからのコメント
1、国会議員の先生方こそ、真っ先に生成AIを取り入れるべきではないでしょうか。
自治体で議事録や企画書案の作成に活用されているのですから、国会の答弁作成や資料整理に応用できれば、効率も格段に上がるはずです。いまだに紙と手書きメモで動いているようなアナログ体質のままでは、国民生活のスピード感と乖離する一方です。もちろん誤情報や機密管理のリスクはあるにせよ、それは技術の導入設計次第で十分に防げる問題です。むしろ、国の最高意思決定機関がAI活用の先陣を切らずにどうするのか、という疑問さえ感じます。国民に「デジタル化」を求める前に、自ら率先して変わる姿勢を見せていただきたいものです。
2、生成AIは書類のフォーマットとか議事録の要約とかは飛躍的に効率化できると思う。使わない手はない。大事なのはファクトチェックですよ。そのファクト自体の調べ方、学び方も今後重要になりそうですね。
3、自治体と関わる仕事をしていますが、横須賀市などの果敢に新しいことにチャレンジする自治体はかなりAIなどを使っていますが、大半の自治体はAIM以前の問題では、いまだに紙だらけ、フロッピー、CD-Rの世界でとてもAIM遠リスクコントロールも含めて使いこなせるリテラシーも人材もいませんよ。
厚労省が雇用保険に加入している人を対象にスキルアップ研修に補助金を出してAIM研修などに利用されているが、これは民間ではなく自治体職員も対象にした方が良い。
4、日本の生成AIって海外の有名モデルを基盤にしていると思うのですが、その基盤データの中にすでに個人情報が組み込まれているので、今更追加で個人情報を入力しないとしても遅いと思います。使えば使うだけ電力と水を使うので、地球温暖化が今までより急速に進み人間が住めなくなってしまいますよ。アメリカなんかはデータセンターの電力消費と水不足でかなり深刻になってますね。生成AIを使い続けた人間に精神的にも依存症が出たり、能力が下がったりと悪影響がでてきてるので、一時的にはコストカットできて効率が良くなったように思う人もいるかもしれませんが、将来的には状況が悪くなりますよ。生成AIは正しい情報データだけを入力しても必ずハルシネーション(AIで生じる間違い・ウソ)が混じるので人のチェックが欠かせませんが、人を育てなければその間違いを指摘できる人間もいなくなります。
AI翻訳とか間違いだらけですし。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/e6b5c733400e14cb0e02423b0cbd3abad8ecb982,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















