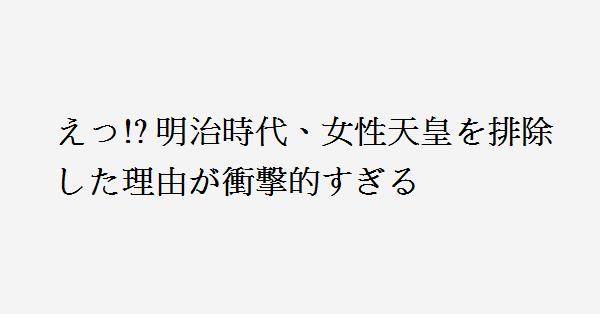
明治時代に制定された日本の皇室典範は、皇位継承を男系男子に限定する内容であり、その背景には男尊女卑の儒教的影響とプロイセンの法制度が影響している。明治政府は、プロイセンの軍事的な男系主義を模倣し、皇位継承を男子に制限した。この決定は、儒教に基づく社会秩序を反映したものであり、またプロイセンのサリカ法典を参照している。サリカ法典では女性君主を認めず、これが後のドイツにおける王位継承においても強く影響を与えた。
しかし、近年では女性の王位継承を否定する根拠に疑問を呈する声も増えており、歴史的には女性君主を容認する社会も存在していた。

このような歴史的背景を踏まえると、日本の男系継承制度は独特なものであり、世界的な潮流とは一線を画している。
日本の皇室典範は、近代化を進める中で女性の皇位継承を排除し、男性による継承を絶対視しました。この政策は、プロイセンや儒教の影響を受け、当時の社会において強固な男尊女卑が背景にあります。しかし、世界では女性君主が普通に登場しており、特に欧州では女性が国を治める例が多く見られます。近年の研究では、プロイセンのサリカ法典の解釈が過剰に男性優位に解釈されてきたことが指摘されており、女性による王位継承の否定が無理な解釈であったこともわかっています。
現代においても日本は、女性天皇の実現に対して慎重な姿勢を見せていますが、世界的に見れば時代に逆行していると言わざるを得ません。
これからの皇室改革には、歴史的な背景を見直し、時代に合った柔軟な制度の変更が必要だと強く感じます。
ネットからのコメント
1、英国のエリザベス1世も運と実力を兼ね備えた偉大な女王だけど、16世紀で女性君主というのが余計にすごいと感じる。他にもマリア・テレジアとか、最近ではエリザベス2世など、ヨーロッパは優れた女性君主が何人もいた。
2、日本が男系男子を維持出来たのは側室があったからで、一夫一婦制になった今、何が何でも男子の出産など体外受精でもしない限り無理なことです。天皇家、且つ、男子という該当者がいない現在、性別を問わない天皇家の長子か、傍系の男子か、という選択になります。天皇家の長子は天皇の血を引き、天皇の器としての教育もなされ、国民との交流でも海外要人でも外交にも、期待と人望を集めておられ、国民の象徴たる人物に相応しいお方。一方は天皇の血を引いてらっしゃるのか、天皇の器として教育されたのか、国民の象徴を特権以外にお持ちの方かという疑問が残ります。明治という一時代の皇室法典を改正し、天皇家長子に皇位継承されることを希望します。
3、天皇陛下の男系男子に拘ると、人格や品格等足りなくても有無を言わさず、天皇が誕生します。具体的に天皇陛下の直系長子であれば、男系女子で相応しい方がおられます。敬宮さまは天皇陛下を間近にご覧になられ、先の戦争の悲しみや、また世界平和を願っておられます。世界との外交が可能で語学に抜きん出た方でないと、国の象徴とはなり得ないと考えます。
4、それでもハプスブルク家は家の主としてはマリアテレジアを主に選んだんですよね。だから家名も変わってないし。日本の皇室はわざわざ姓がないと言う世界的に見ても特別仕様で、男女どちらが継いでも家は続くようになっています。だから古代は男子女子関係なく主に立てたし、女性君主から考えた関係性で後継者も決められたのです。男系男子にこだわれば滅びるのは早いこと、直系からの血筋がより離れやすいことがわかっていたのです。古代の人にわかっていた事を今の政治家がわからないとは愚か過ぎます。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/06bffbea2529b99a140c24d6d3406b22e471607a,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















