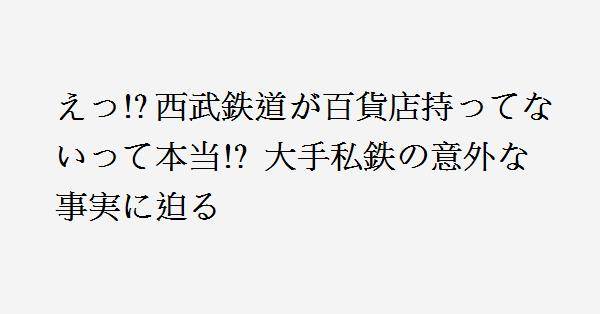
多くの大手私鉄グループは鉄道事業だけでなく、百貨店事業も手がけているが、一部の私鉄はこの事業を持たない。阪急が日本における鉄道と百貨店の融合を始めたのは20世紀初頭であり、現在では東急を含む多くの私鉄がこのモデルに従っている。しかし、2025年現在、西武鉄道、東京メトロ、相模鉄道、南海電気鉄道、西日本鉄道といった5社はグループ内で百貨店を運営していない。
相鉄と南海は横浜駅と難波駅にテナントとして百貨店を持ち、西鉄は福岡(天神)駅に三越を入居させ、過去に井筒屋と深い関係があった。西武鉄道は「西武」ブランドの百貨店を運営していないが、昔の西武百貨店は西武鉄道と同じグループだった。

この状況を考えると、ビジネスモデルの進化や鉄道と商業の結びつきに批判が必要だと感じる。このような変化は伝統的なビジネスモデルの崩壊を示している。阪急や東急のような企業が、鉄道事業と百貨店経営を組み合わせて成功を収めたのに対し、多くの私鉄がその方向に進むことを選ばないのは、事業戦略や市場の変化に起因する。しかし、問題の本質は、鉄道事業者がただ運輸だけに留まっているわけではなく、消費者の関心や需要に応じてどのように多角化していくかという対応力にある。解決策として、1) 鉄道と商業施設の結びつきを再評価し、消費者の移動と購買行動を一体化させる新しいビジネスモデルの開発、2) 地域密着型の商業施設との連携強化、3) デジタル技術を活用し、オンラインとオフラインの融合を図るなどが考えられる。
このような動きは、ただの運輸以上の価値を消費者に提供し、鉄道業界と商業の結びつきを再び強力にする可能性があるだろう。鉄道会社の役割とその未来は、まさに私たちの生活環境の転換に直結している。
ネットからのコメント
1、南海は記事の通り南海難波駅に髙島屋の大阪店が入ってますし、閉店した髙島屋和歌山店は南海の和歌山市駅の駅ビルに入ってましたし、来年1月に閉店の髙島屋堺店も南海の堺東駅の駅ビルに入居していて、髙島屋泉北店も南海が子会社化して合併した旧泉北高速の泉ヶ丘駅前にあるので、南海沿線民にとっては髙島屋は南海の百貨店代わりのような存在です。
2、西武百貨店は西武鉄道とはグループではなくなったが、西武鉄道系の埼玉西武ライオンズを応援したり、そもそも本店と所沢店が西武王国の街にあるから、切り離せない関係ではあるよね
3、名鉄も今や名駅の1店舗のみですよね。来年名駅再開発に伴い一時閉店するそうですが、事業としては今後百貨店を持たない可能性もありますね。
4、水戸京成百貨店はコロナ禍で大規模な助成金搾取を行いましたが、行政当局も県民もさして騒ぎ立てず現在も盛業中です。
つくばから西武が撤退した後、同店は茨城県唯一の百貨店になっていますので、あまり叩いて閉店されると県のメンツが潰れるのでしょうね。オンリーワンは強いです。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/3ea8908fdc58bf2bdf85a12395855e5375d164cc,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















