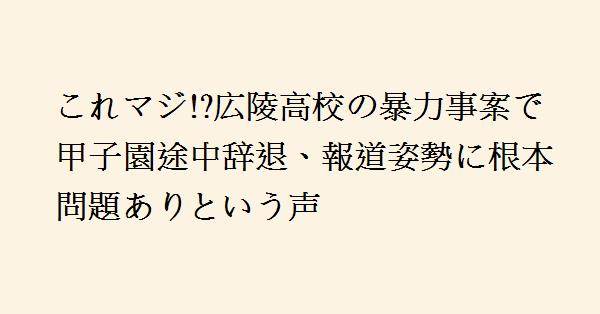
広陵高校が暴力事案をきっかけに夏の甲子園大会途中辞退を決定したことが波紋を広げている。辞退理由として学校側はSNSでの情報拡散や脅迫による安全問題を主張。しかし、この背後には私立高校の「隠蔽体質」が存在するという構造的問題が明らかとなった。事件は元部員の保護者がSNSで暴力問題を発信し、学校の対応が批判を浴びる形で公になった。
報道姿勢に関しても批判がされ、いじめ防止対策推進法における自治体の監督限界が露呈した。この事件は私立校の隠蔽体質と法制度の欠陥が絡む社会問題として注目されている。

広陵高校の問題は単なる高校野球の枠を超え、教育制度全体に広がる根深い課題です。まず、私立学校における隠蔽体質は、いじめ防止対策推進法の限界を示しています。この法律は重大事態の報告義務を定めていますが、その判断は学校に委ねられており、結果として不正が隠蔽されやすい環境を作り出しています。ではどうすれば良いのでしょうか。第一に、学校に対する自治体の監督権限を強化し、報告の透明性を確保する必要があります。第二に、私立学校の自主性と公共性のバランスを見直し、法制度を改善することです。第三に、メディアは偏った論調を避け、被害者の心理的ケアも含めた公正な報道を行うべきでしょう。
隠蔽体質を放置すれば、教育の価値が損なわれ、未来の世代に悪影響を与えます。社会全体で解決策を模索し、より公正で安全な学びの環境を育てることが、教育制度において暫定的な課題です。

ネットからのコメント
1、「無償化」するなら公立校並の透明性の担保をという論点は勉強になりました。私学には、私学自由の原則により引き続き自治体の監督権が及ばないのは当然ですが高野連には報告しても県には報告しないというイジメ対策法への逸脱がされるとは想定されておりませんでした。まず、この法律には、対応不足に対する罰則がありませんがイジメを防止するという観点では罰則が必要です。また、県から調査形式に踏み込んだ調査命令を出すのではなく第三者委員会の情報を共有するようにとの対応になっているのは、県に報告が来ないと何もできず、立ち入り検査をしたり、報告命令を出すことが想定されていないためです。
また、私学でこのような抜け道探しのようなことができるのは第三者委員会を自分の財布で設置することができるからで、公立だと、各学校には予算権がないので、必ず報告する必要が出てきます。県の関与策と罰則について強化する必要があります
2、本来、高校野球も高校の部活の一つで教育活動が基本のはずだ。それが本末転倒で甲子園出場の為に教育を軽視している。高校野球が営利と結びついて学校も生徒の人間教育を無視している現状がある。SNSの問題はあくまで二次的問題で根本には過熱した甲子園ビジネスが問題なのではないか。
3、校長や監督からは、自分達に非があるとの認識は一切見られない。生徒からすれば、恐怖でしかない。いくら自分が正しく、家族も同調してくれたとしても、学校側は一切受け付けない。下手をすると、事件の責任までなすり付けられる。抵抗しても無駄と言う意識の中で、諦めて退学を選択していく。こんな人権侵害が平気で行われている学校に、税金注入して無償化などあり得ない。校長も監督も、一刻も早く生徒や選手を守るべきだろう。被害者に対する謝罪はもちろん、恫喝、隠蔽の事実が無いのなら、ハッキリと無い旨主張し、あったのなら、選手の行動は自分達の行いに原因があるとして、全責任を負えば良い。
その点は、他者への確認も要らない。逃げ隠れして、選手を世間の批判に晒し、騒動をSNSの責任にする教育者として有るまじき姿勢。このまま現職を続けられる訳がない。
4、過去に多くの脱税や裏金の問題が発覚しているように私立高校は実際には営利を目的としている企業と何ら変わらない。その中で野球をはじめとした部活は広告塔として大きな役割を果たしており、経営的視点から隠蔽を図る経緯も理解できる。性善説的視点から公益法人だからといって甘やかすことなく、行政や外郭団体が厳しく取り締まっていくことが必要だろう。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/e7a69b89fb52cb62dbf8098b4518d810536465f3,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















