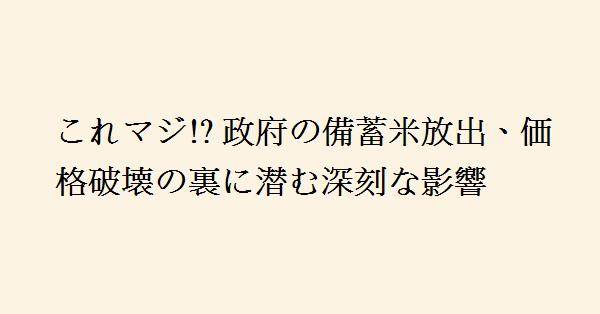
2024年春から全国的にコメ不足が顕在化し、特に新潟県でも8月には店頭からほぼ消える事態に。農水省は当初「流通の目詰まり」と判断し、2025年1月に21万トン規模の備蓄米放出を決定。その後、目的を価格高騰対策に変更し、5kg2000円を目標に随意契約で小売りへ放出。しかし新米が出回る時期に備蓄米がだぶつき、生産者米価低下や販売遅延(約2万9千トンがキャンセル)への懸念が高まった。
8月5日、政府は生産量不足が原因だったと公式に認め、増産へ方針転換した。

政府の判断の迷走は、農政の信頼を深く損なった。備蓄米は災害時の命綱であり、価格調整の道具ではない。それを市場原理を無視して大量放出し、結果的に生産者と流通業者を同時に追い詰めた構図は異常だ。本質は、需給予測の甘さと政治的介入の優先順位の誤りにある。対策は、①需要・生産量のリアルタイム監視と予測精度向上、②備蓄米の放出条件を厳格に法制化、③市場介入は透明性と期限を明確にし、生産者への補償制度を整備することだ。食料安全保障は政争の具ではなく、国民の生命線だ。今回の失敗から学ばなければ、次の危機では「米」そのものが机上の幻になる。
ネットからのコメント
1、そも、備蓄米の取扱いについてな~にも決めてなかった事が明らかになりましたね。
なぜ米を備蓄するのか。どこに、誰が備蓄すりのか。どのような時に放出するのか。放出する際の順番はどうするのか。(危機管理としての扱いであれば、古いものから放出するのが当然では?)放出する際の価格はどうするか。(買い入れた価格で放出すべきでは?)放出する際の物流はどうするか。国民への販売はだれがどのようにするのか。等など、色んな状況を想定し、ある程度具体的に予め決めておくべきではありませんか?いつむ臆面もなく聞かされる「想定外でした」という言葉で済まされものではありませんよ。
2、新米が出ても、価格が下がらなければ、安い米を求める人が多ければ市場の原理で安い輸入米が店頭に並ぶのが普通になるのでは。備蓄米も必要な人たちがいつでも必要なだけ買えるのは悪いことではない。
3、参議院議員選挙が終わってから、あれだけ叫ばれていた【備蓄米】【米の平均価格】がテレビの報道から一斉にほとんど絶え、【就職氷河期世代の救済】は政治家の口から出なくなりました。政治の流れによっては解散総選挙ですが、そうなれば再び聞けるようになるのでしょうか。
選挙のない時期に、それぞれの政党や政治家がどのような行動をしているか、どんな言動を発しているか、耳を凝らしておけば、有権者はいつ何時選挙があっても、迷いなく投票出来る素地をつくることができるのではないでしょうか。
4、んーあまりにも通常とかけ離れた金額の高騰があればそれは非常時と言うことで良いと思います。金額が上がりすぎて消費者が消費できなくなれば非常ですので。そういった意味では備蓄米の放出は正しい行動ですが、今後コメの生産量が大きく落ちたらどうするかは考えておいて欲しいですね
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/435c94bb7c6d100aa88952731cbbaf554972f1bc,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















