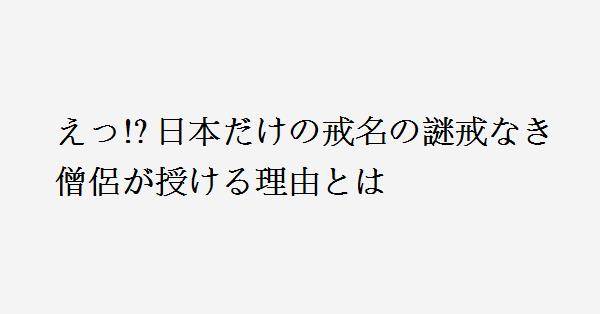
事件概要:日本の仏教界における戒名制度は、他の仏教国と異なり一般の俗人が死後に授かるものであり、これが日本独自の制度となっているという問題が指摘されている。戒名は本来、仏教徒として守るべき戒律を授け、仏弟子となる証として与えられるものだが、日本国内では妻帯し酒を飲む僧侶が戒名を授けており、現状と仏教の教えとの矛盾を招いている。
寺の住職・高橋卓志氏は「戒なき坊さんから戒名を受けることに根本的な問題がある」と批判し、葬式の際に授戒が行われることの意味について疑問を呈している。

コメント:日本の仏教界における戒名制度の矛盾は、多くの人々の死生観に影響を与える重要な問題です。戒名が一般の俗人にも与えられること、そして僧侶たちが戒律を守らずに破戒の道を辿っている状況は、葬式が戒律の厳格さや仏教の純粋さを失わせていることを示しています。この制度の本質的な欠陥は、宗教的な戒律の意義が曖昧にされている点にあります。解決策として、まず僧侶が戒律を厳守することを義務付ける制度改革が必要です。さらに、戒名制度の意義を社会に正確に説明し、その運用方法を見直すこと。そして葬式の質を改善するために僧侶と遺族との対話を強化することが求められます。
この制度が変わらなければ、仏教の教えの深さを理解することは困難です。日本の葬式仏教が真の宗教的精神を取り戻す日はいつ来るのか、今こそ改革が必要です。
ネットからのコメント
1、肉食べて、色を好み、酒も嗜む。そんな坊さんは五万といるよね。檀家の数によって違いはあるだろうが、ウチの近所のお寺では、親子で僧侶、おくりさんの3人で、ベンツ、レクサス、アルファード、大型バイクを所有しつつ、葬儀や法事にはプリウスや原付で向かう。そう考えると、何となく伝統だから、戒名と言う制度は継続してきたけれど、ありがたみもたいしてないし、拒否する人も出てくるんだろうね。それも時代の流れで仕方ないと思う。
2、お寺さんもそろそろ考えるべき時がきているのでは?宗派によってはお寺の仕事以外の仕事はしてはならないと聞きました。一生懸命働いて、親の葬儀、戒名代で私の半年のパート代は領収書も無く無くなってしまう。敬われるのが当たり前と思っている僧侶も、はい、この金額です。ではなく、葬儀、お参りのない日はこの時代、タイミーで少しは仕事、お金の大切さ、世間の厳しさを知られた方がよいと思います。
3、ついでに言うと、法要も、原始仏教にはありません。仏教が中国に入ったとき、中国の古来からの土着の先祖崇拝の儀礼を取り入れたものと考えられます。檀家制度が創設された日本では、法要を行わないといけない回数が中国のそれよりも増えました。檀家制度により、仏教は僧侶の生業となり、法要の際のお布施は重要な収入源だからです。
4、いわゆる戒名料に関しては思うところはあるけど,日本仏教なんて昔から結構いい加減なものだと思うがそれでいいのでは。浄土真宗では非僧非俗とも言われ,修験道では半僧半俗とも言われているが,いつの間にか他宗でも妻帯飲酒は当たり前になっていった。もっと言えば国家神道以前は日本の八百万の神も仏と混然一体になっていたわけで,そういう緩い宗教観,価値観がこの国を一見何となくだがしっかりとまとめてきたんだと思う。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/1dcb8c8375e9d6b79faa6880a8733b5baf1233fe,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















