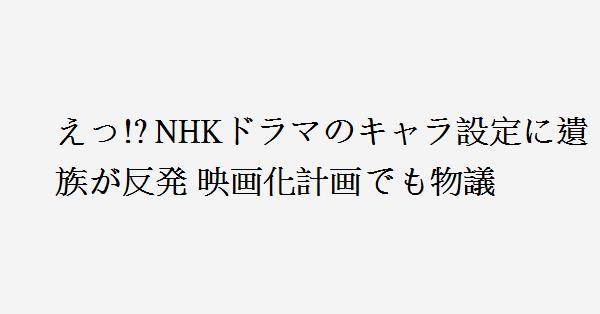
NHKが戦後80年関連のドラマ「シミュレーション~昭和16年夏の敗戦~」を16、17日に放送しましたが、登場人物の設定に基づくキャラクターが実在の人物のイメージを損なうとして議論を呼んでいます。描写された所長は議論を阻む役柄として設定されましたが、実際は自由な議論を奨励する人物だったとされています。遺族はこの違いが誤った歴史認識をもたらすとし、NHKに対しフィクションであることを強調するよう求めました。
放送後も誤解が生じたとし、遺族はBPOへの申し立てを検討中です。

今回のNHKのドラマ化に際し、その責任感不足は否めません。現実の人物をモデルにしつつ、実質的な所業を覆すようなフィクション描写を行うことは許されるべきではありません。特に歴史を扱う作品では、表現の自由の名の下で誤解を招くような描写は、一線を越えたものであると言えるでしょう。これにより、視聴者に正確な史実が伝わることを妨げてしまっています。
その問題を解決するにはまず、フィクション性をより明確にすることが不可欠です。放送前に伝えるだけでなく、番組自体にも繰り返しその表示を行うべきです。また、フィクションと史実の違いを解説するガイド番組を設け、視聴者に理解を促すことが有効でしょう。そして、今後の作品制作においては、遺族や専門家との事前協議をしっかり行い、その意見を尊重する姿勢が求められます。
この事件を通じて、芸術表現の自由と歴史的事実を見誤ることの危険性が鋭く対比されます。放送局としての責任は重く、その影響力を考慮した上で、正しい歴史認識の確立に繋がる作品を提供するべきです。
ネットからのコメント
1、確かにあれは酷かった。楽しみにしていたけど、後編は観なかった。番組の最後に史実と照合していたのにはNHKのせめてもの良心を感じたが(NHK当局も完成したドラマを観て愕然としたのでは?)、なぜあのような改変を行う必要があったのか全く分からない。30年以上前に、同じ題材を民放がドラマ化したと記憶するが、あちらのほうがよほどまともだった。史実に即してやればよいものを、わざわざ手間暇かけて改ざんして、遺族の心情を傷つけ、却ってつまらなくした必要性が全く分からなかった。
2、映像を視聴すると、ラジオや読書と違い映像がそのまま記憶として残るので、いくらテロップなんかで「所長はフィクション」なんて最後に流しても、そこは残らず「あの研究所の所長はひどいやつだった」という部分が後に残る。遺族側の反発は当然で、制作者はちょっと浅はかだったのではないか。
特に戦時中でいろんな思いがうごめいていた時代は、もっとそれぞれの人物像を慎重に扱うべきだったと思う。
3、どのような人柄か知らなかったから話がドラマチックになるように創作したと言うのならば、100歩譲ってまだ許せる。人柄を知っていたにもかかわらず話がドラマチックになるように改ざんしたのであれば、あきらかに超えてはいけない一線を越えている。この件は、もっと大きな場で糾弾されるべき。
4、NHKのドラマはこの件に限らず、朝ドラや夜ドラ、大河ドラマさらにはドキュメンタリーなど極めて偏向していると思わざるを得ない。先に思想的、政治的な目的や結論があり、それに向けて巧妙な編集で国民の潜在的意識改革(改悪)を目指していると感じる。フィクションだからという言い訳はあり得ない。実在の人物を描く場合、その人物像を都合良く利用すべきではない。このドラマの場合、軍部の好戦体制を強調するために、人権を無視し卑劣な軍人像として描いており決して許されることではない。NHKの人事を一新し編集体制の大改革を強く望む。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/37dd6bcd2c36a0b5620d9afbd079e5ac879b5934,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















