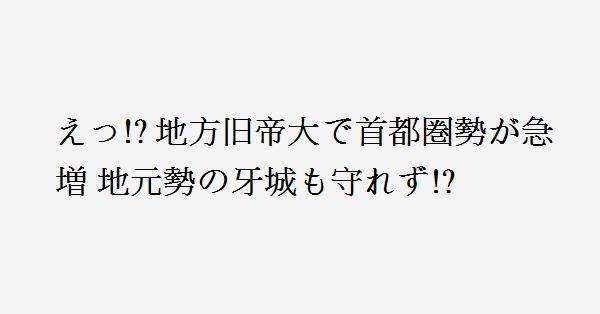
この報告書は、日本の大学進学における地理的な変化と教育格差の拡大を示しています。首都圏の高校から地方の旧帝国大学(北海道大、東北大、京都大、九州大)への進学者数が2012年から2020年にかけて急増しました。具体的には、北大は361人から583人、東北大は375人から620人、京大は244人から365人、九大は61人から129人と増加しています。
これは、首都圏の中学受験熱が高まり、地方の大学への進学が現実的な選択肢となっていることを示しています。この変化は、地域の教育資源格差や人口減少が背景にあるとされ、首都圏勢が地方の進学者を押し出している状況です。さらに、地方の医療機関への就職が進まないことが地域医療に影響を及ぼしています。

この状況は首都圏と地方の教育格差や地域医療への影響を物語っています。首都圏から地方大学への進学者の増加は、地方の優秀な学生を締め出し、地域密着型教育の意義を損なっています。医師不足を抱える地方において、地方大学の医学部が「教習所」と化している現状は由々しき問題です。まず、地域枠入試の強化が必要です。これは、地域出身学生の積極的な入学を促し、地域医療への貢献を促進します。地方の進学校への資源配分を見直し、首都圏との教育格差を縮小することも不可欠です。
さらに、地方大学と地域社会の連携強化を通じて、卒業生が地元へ戻るインセンティブを与えることが求められます。このような具体策の展開があれば、教育の地域格差が是正され、多様な知識が地域社会に還元されるでしょう。教育の平等性を確保することが、日本の未来をより明るくする鍵となるのです。
ネットからのコメント
1、旧帝大が揃った昭和初期は人口が全国にばらけていたのですが、その後首都圏に人口が集中し続けたので、有力な国公立大が相対的に少なくなり、地方の旧帝大に流れる傾向はかなり以前から有りました。ただ近年の急速な増加は、首都圏の有力私大に自宅から通ってもらうより、国公立の方が学費が安いので一人暮らしで余計にお金が掛かってもトータルで安く済むと判断されているのでは? 医学部は特に学費の差が激しいので地方国公立が選ばれているのだと思います。
2、山口大学医学部医学科にも東京、静岡とか全国の進学校から生徒が集まってる。それは山口に限ったことではない。全国の国公立医学部医学科の入れるところならどこでも入りたい人がいっぱい。そこで医者になれば一般枠ならどこでも医者になれる。
医者は辞めてもいくらでもまた医者として再雇用されるし何歳までも働けるから男女問わず大人気。
3、首都圏よりそれ以外の方が少子高齢化が進んでいるのはその通りだが、それだけじゃないと思う。やっぱり国立大学と私立大学では学費の差が大きいのもあるだろう。特に東京の私立大学で一人暮らしとなると学費だけでなく生活費だって高くなる。それならネームバリューのある旧帝大のほうが学費も生活費も抑えられるというところでは無いだろうか。
4、地方大学を進学先に選ぶこと自体は良いことだと思いますが、卒業後に多くが首都圏へ戻ってしまうのはやはり課題です。地域枠は強制力が弱く、学力低下の懸念もあるため決定打にはなりませんが、何もしなければ人材流出は続いてしまいますね。さらに学生だけでなく、若手教員も研究環境や生活の利便性を理由に都市部を選びやすく、定着が難しいのが現状です。奨学金免除や就職支援に加えて、研究や教育の環境を整えるなど、地域に残る魅力を高める仕組みを少しずつ積み重ねていく必要があるのでしょうね。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/f8aa43bd01391f33802f27f48096c5775ba2bcf8,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















