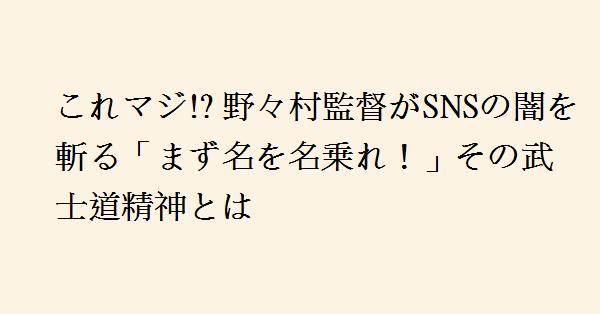
8月14日、甲子園で行われた全国高校野球選手権の2回戦で、開星高校(島根)は仙台育英高校に6-2で敗れ、初の甲子園2勝には届かなかった。開星の野々村直通監督(73)は、広陵高校(広島)の過去の暴力事案に関連し、SNS上で一方的な攻撃や真偽不明な情報の拡散が問題であると指摘した。彼は匿名の批判や陰口が卑怯であるとし、武士道に基づく名乗り出る文化の必要性を強調。
いじめ問題の解決にもつながると述べた。

この発言は、現代社会におけるSNSの利用方法や匿名性について考えさせられるものです。匿名での批判や攻撃は、往々にして非常に陰湿で自身の意見に対する責任を果たしていません。また、情報の真偽が不明確なまま拡散されることにより、風評被害が生まれるリスクも顕著です。これらの問題を解決するには、まずSNSプラットフォームが情報の信頼性を確保するための仕組みを構築することが重要です。次に、学校や家庭でインターネットリテラシー教育を強化し、情報の取り扱いについて考えさせることです。そして、法的枠組みの整備によって、誹謗中傷に対する監視と罰則を強化することが求められます。このように、真偽不明な情報を見極め、自身の発言に責任を持つことが、現代のネット社会における新しい武士道の形として求められるのではないでしょうか。
ネットからのコメント
1、今回の問題、SNSが無ければいじめの被害者の声は封じられていたチームメイトも、先生も、監督・コーチも、広陵高校も、果てには広島県警も誰一人としてSNSで被害者自身がSOSを発信するまで被害者の味方にならなかった、これがどれだけ当人達を絶望させたかSNSに功罪があるのは理解する、ただ本来守られるべき被害者が守られない、法治が真っ当に機能しないのであれば今後もこのようなSNSの使われ方は拡大していくだろう
2、それを言うなら、まず加害者が名乗り出て明確な謝罪を口にする事から始めるべき。暴力事件やいじめについて未だに学校側、高野連側からも公式な謝罪や遺憾の意が表明されていないのでは?
3、気持ちは分からなくもない。私も匿名のSNSの行き過ぎた発言については「匿名だから言えるのだろうな」と思う(ここ、ヤフコメもそうだが)しかし今は広陵を擁護するようなコメントをひかえるべきでしょう。「武士道」という言葉を出すあたりが高校野球の体質を表している。もうそろそろ野球部は変わるべきだ。野茂、イチローが大きな転機になったと思う。
その後の大谷もそう。指導者、上に立つ人間の古い考えを押しつけそれに従順に従うのが良いというような考えはなくしたほうがいいだろう。上が押し付けるから下に押し付けようとするのもあると私は考えています。
4、被害者が声を上げているにも拘らず、高校や高野連は無視を決め込んだのがそもそもの原因で、「「自主・自律」をモットーに、「フェアプレー」「友情」「闘志」という「三つのF」を、野球を通じて若者たちが体得できるよう努力していく」という高野連のモットーも全く機能していないから、SNSで声を上げているのでは?SNSは広義の署名活動のようなものだと思う。法律的に問題があるのであれば発信者情報開示請求などで対応すればよい。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/08e567a070d6c2d2b9bf665822e2cbb5fa47e1d4,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















