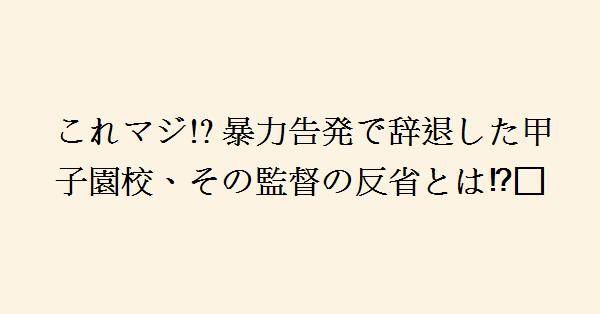
2025年、夏の甲子園で広陵高校がSNSで暴力行為を告発され批判を受けました。1回戦を勝ち進んだものの、この騒動の影響で2回戦を辞退。この事態を受け、35年間監督を務めた中井哲之氏の退任も決定。甲子園常連校の日大三高の前監督・小倉全由氏は、監督の姿勢によって「対戦したい学校」と「対戦したくない学校」が分かれるとし、監督が選手にマナーや情熱を浸透させるべきだと主張。
高校野球の指導法見直しが進む中、今回の騒動は指導者のあり方に焦点を当てる契機となりました。

野球界における監督の指導方法が問題に挙げられることから、この内容は深く分析し批判案を提案することが求められます。個々の指導者が選手をどのように育てるかは、学校の評判やチームの士気に直結します。批判的なトーンで、指導法の欠陥に切り込みます。

高校野球の舞台で選手に対し暴力や不当なペナルティを行使する行為は断じて許されません。監督が選手に対して尊厳をもって指導を行わない限り、学生スポーツは本来の育成の場としての機能を果たし得ません。
まず、指導者に対する指導と倫理教育の強化が不可欠です。トレーニングを通じ、学生の心を育む姿勢を徹底すること。そして、教育機関は監督の行動を監視するシステムの構築を急ぐべきでしょう。さらに、暴力や不適切な指導を告発するための安全で匿名性の保たれた報告システムを学生に提供する必要があります。野球の試合をただの競技以上のものにするには、教育者が公正で誠実であり続けなければならないのです。


ネットからのコメント
1、そもそもスポーツは本人がやりたいからやるのであって、試合でミスをすれば一番傷つくのは本人です。
指導者は見込みがあればミスの原因を指摘して指導し、そうでなければ試合に出さないで十分です。高校時代はサッカーで毎年県大会のベスト8以上の中堅校でレギュラーでしたが、そのような指導者に恵まれ、楽しくサッカーが出来ました。練習試合で全国常連の強豪校に勝った時は、こちらが大喜びする一方で対戦チームからは監督コーチの怒号が聞こえ、グラウンド横で罰ダッシュを繰り返していたのを見て、こんなことをしてまで強くなりたいとは思えませんでした。人生は長く、高校の3年間などあっという間に終わります。罰を恐れて競技をした選手が社会に出て大成するとは到底思えません。
2、最近は絶滅危惧種ですが、自身の権威をひけらかすかのように、部下や若手を立たせて永遠と叱責する人もいましたね…、それと同じ心理なのかと思います。見ていて気持ちの良いものではないですし、練習試合を断るのはよくわかります。
3、ありましたね。私が見たのは、今でこそ強豪私立になりましたが、当時は弱かった。試合で最初に三振した選手はそのイニングが終わるまでひたすらダッシュしてました。
当時ピッチャーやってて相手の1番バッターから三振取ったのですが、その後から制球が定まらずビッグイニングになった試合でした。選手はヘロヘロになってましたね。これも指導なんでしょうね。私には理解が出来なかった••••••••
4、ペナルティなんて、選手が萎縮するだけで個人で考える力を失わせるものですよ。確かに恐怖政治で選手をマシーンの如く統率して戦えば勝てるかもしれない。実績だけがほしければそう言うやり方もあるかもしれないけど、選手の教育面で見れば最悪だ。この様な自分の為に選手を消費する指導者は1日も早く退場して欲しい。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/1e29d725bacc30d1eb344f98e82e44c1715daa4c,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















