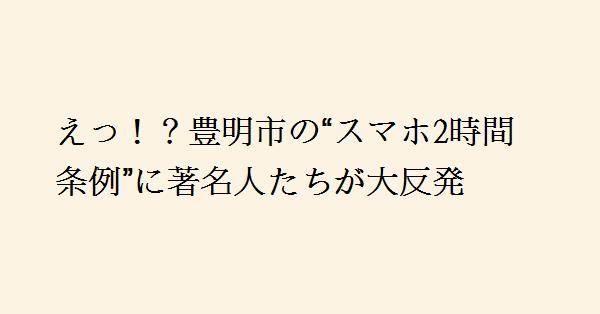
愛知県豊明市が9月の定例議会で発表した新条例案は、スマートフォンなどの使用を仕事や勉強以外の余暇時間に「1日2時間以内」とすることを推奨するものだ。条例可決後の施行は10月1日で、罰則は設けられていない。SNS上ではこの条例案に対して意味や効果への疑問が巻き起こり、有名人からも反応が多く寄せられている。経産官僚出身の岸博幸氏は、家庭内での指導の重要性を説き、保育士のてぃ先生はスマホが現代の子どもたちにとって必要なツールであることを指摘。
市長の小浮正典氏は「2時間」の些細な指針だとして市民にバランスのとれた生活習慣を考え直してほしいと声明を出した。

この条例案はただの形骸に過ぎないが、深刻な背景を浮き彫りにしている。つまり、現代社会が育児環境の整備を怠っていることだ。まず、働く親が子どもと十分に過ごせる時間を確保できる制度の考案が急務だ。第二に、子どもがのびのび遊べる公共空間の改善でスマホ依存を減らすことが考えられる。また、教育機関や地域社会が共同でデジタル教育を進め、スマートフォンの利点と欠点を子どもたちに教えるべきだろう。これらの根本的な改革なしには、ただ時間制限を設けてしまうだけでは何の効果も生まれない。豊明市は表面的な対策ではなく、本質的な問題を解決するための道筋を示さなければならない。育児を個人に押し付けるだけの姿勢は未来を見据えた行動とは言えない。
社会全体が手を取り合い、家庭をサポートする仕組みを築くことこそが、真に価値ある解決への鍵である。
ネットからのコメント
1、15年くらい前まで問題になっていた「ナゾの校則」のメンタリティそのものだね。「我々は管理する側。子どもは善悪が判らないから、我々が型にはめなくてはいけない」って?行政側は「しなくてはいけない、とは、言ってない。努力目標、あるいは目安を定めただけだ」と言ってるみたいだけれど、それをわざわざ「議会で決定」?ほかにやることがあるような…。ただ、自治体の住民のなかには「自分たちの判断が難しいことは、議会で決めてもらったほうが子どもへの説得力をもたせられるし、ありがたい」と語っている人もいたという記事も読んだ。(本当にいたのか、記者がつくりあげた人物か知らないけれど)。そういう「すべてお役所が判断してくれるとラク」という人がいるとするなら議会はそうした住民のためにこの条例をつくったともいえるかも。自分の子どもの教育は、親が考えてすべきと思うけどね。
2、就活で会社の面接にきた大学生が、待ち時間に音出して動画観てて面接の前に帰されたとか・・・。
そういう想像力が無い人のために問題提起したのではないでしょうか?今更ながら「自由と身勝手」の違いがわからない人が増えすぎて怖いですよ。
3、お役所らしくない仕事だったと思う。多様性の時代、価値観が多様な時代、物事を中々決められない社会だ。スマホの価値観を超越して健康を優先選択した。罰則は無いらしいが中々出来ない果敢な決断だと思う。
4、問題提起はいいと思いますけど地方政治が予算と時間を使ってやる事じゃないですまず、細かなリサーチは有ったんですかね主な対象であろう若い世代に条例が有ることで効果が有るのかヒアリングしたんですかね
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/4c3a8cc653472f1ea16f7242d3425a830c4dbacd,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















