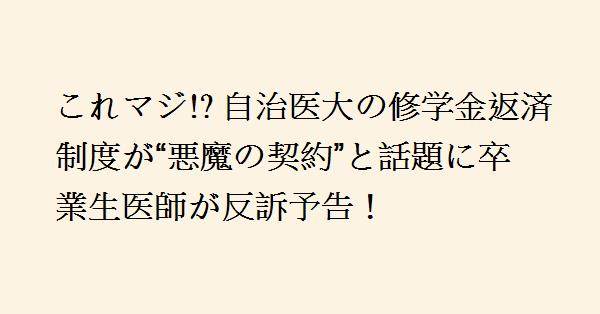
事件概要:
2025年8月6日、栃木県の自治医科大学を卒業した医師A氏が、同大学および愛知県を相手取り、修学金制度の違憲性を問う訴訟の第2回口頭弁論が開かれた。A氏は2015年に入学し、2660万円を貸与されたが、指定病院を退職したため、損害金1106万円を含む計3766万円の一括返済を求められている。
A氏は、契約の拘束性と高利息が憲法や労働基準法に違反すると主張。一方、大学側と県側は正当性を主張し、反訴を予告した。

コメント:
地域医療の担い手を育てるという美名の下で、若者の将来を縛り、経済的に追い詰める制度がまかり通る現実は、極めて異常だ。医師A氏が直面したのは「育成」ではなく、「囲い込み」と「使い潰し」だった。憲法で保障された居住・移転の自由、労働契約の原則、そして消費者契約法の理念すら無視される構造に、制度としての正当性はない。
本質的な問題は、自治医大と都道府県が連携し、若年層に選択肢を与えぬまま将来を縛り、労働条件の不利益を説明せず、退職の自由さえ事実上封じている点だ。しかも、違反すれば高額の違約金と高利息という罰則が待つ。
それは教育支援ではなく、実質的な“経済的拘束”である。
打開策は明確だ。第一に、制度契約時の情報公開と説明責任を法的に義務化すること。第二に、勤務条件の柔軟化と年次ごとの見直し制度を設けること。第三に、一括返済条項に代わる段階的返済や猶予制度の導入が必要だ。
「医師不足」という社会課題を盾に、若者の自由と生活を人質に取るような制度設計は、もはや時代錯誤である。使命感を利用する“美談”の皮を剥げば、その正体は公的支援の名を借りた労働搾取だ。未来ある人材の人生を犠牲にして成り立つ医療に、持続可能性などない。
ネットからのコメント
1、自治医大はそもそも医師不足の地域にも医師を派遣するための大学。説明不足を理由に大学を提訴しているが、入学前に調べたり、入学後に在学生や卒業生などから情報収集をされてこなかったのだろうか。自治医大は最近できた大学ではない。事情があるのは気の毒ではあるけれど、個々の事情を聞いていたら、地方勤務を拒否する卒業生を容認することになるのではないか。自治医大に合格できる学力があるなら、中退しても別の医大に合格できたはず。
国と自治体からの税金をもとに、学費が免除されているのだから、返金を求められているのなら、借金してでも返すべきでしょうね。
2、この大学は、僻地や医療のなかなか普及しづらいところの意思を要請するためにできた大学であって、それをわかった上で入学しているんだからこの人の言い分はおかしいと思う。これ許したら自治医大で税金を使って医者になったけれども、僻地の医者にはならないよと言うような勝手な理屈が成り立つから許すべきではないと思う
3、県庁職員です。県は負担金として毎年億単位の金を払っています。研修医の2年間も給料を負担します。離島やへき地の医療のため、1人の医者を作るために一億以上の税金が使われています。医師免許を取ったら自由を主張するのは横暴です。3千万円どころか一億返済させるべきだと思います。
4、国立の医学部は東大理科1類や理科2類の学力が求めれられ、私立の医学部は下手したら6年間で約4500万円の学費が必要なのに、無償で手当までもらえて医師免許が取得出るのに、それに対する見返りを考えないで自治医大に進学をして、それは悪魔の契約であると法律的に主張すること自体 無責任と考えます。
僻地医療への貢献を考えない人は自治医大に進学をしてはならない。防衛医大についても同様
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/42e99371562be2f9f76a478134f85b2910a46fd2,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















