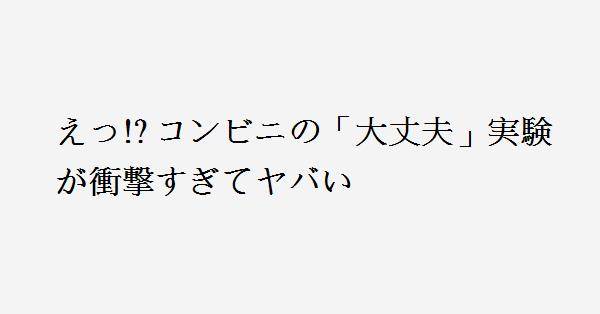
事件概要:
北九州市立大学の准教授であり、日本に帰化した応用言語学者アン・クレシーニ氏が、日本語の曖昧表現「大丈夫」の使用実態を研究。コンビニ店員の「レジ袋は大丈夫ですか?」という問いに対し、客が「大丈夫です」と返答する場面を題材に、別の表現(例:「結構です」)への置き換え実験を実施。
結果として、「大丈夫です」が最も誤解なく通じることが判明。特に「ありがとう」など語尾の違いが意味解釈に影響する点が観察された。実験は日常会話における言語の多義性と曖昧性の影響を浮き彫りにした。

コメント:
「大丈夫です」という表現が、要るのか要らないのか、行くのか行かないのかを一言に押し込めるほど曖昧化している現状は、日本語の美しさというより、言葉の機能不全に近い。これは単なる言語の変化ではなく、意思疎通という本質的な役割が揺らいでいる重大な問題だ。曖昧な表現に依存する日本の対人文化は、相手の意図を察する「空気の読み合い」に過剰に依存しており、それが外国人のみならず日本人自身にも混乱をもたらしている。
この問題の根底には、日本語教育における実用的運用力の軽視、日常会話における明確性への忌避、そしてサービス業界における「クッション言語」信仰がある。
改善にはまず、教育現場での「意味明示」の訓練、業界マニュアルの見直し、そしてメディアを通じた言語意識の啓発が必要だ。
「大丈夫」が大丈夫じゃない今こそ、言葉が持つ明確性と誠実さを取り戻す時だ。意思表示をぼかす言葉が、人と人との距離をさらに広げている。この言語環境の「ヤバさ」に、私たちはもっと真剣に向き合うべきだ。
ネットからのコメント
1、いるか要らないか?を大丈夫ですか?と聞かれたら「ください」「いりません」とはっきり答えています。丁寧なつもりなのか、「レジ袋のほうは〜」とほうをつける人も増えましたが、意味わかりません。お釣りのほうは○○円になりますとか。日本語にもちゃんとした表現があり、断る事を曖昧にする必要なんて無いんです。マジ、ヤバい、超、ショボい、ウザい…これだけで会話してんのかい?と思う事あります。筆者の書いているように「マジ、ヤバ!」が例えば美味しいものを食べた直後に発せられた言葉だとしたら、「凄く美味しい!」と言う日本語を知らない日本人なのでしょう。ちょっと前、若い女性は何でもかんでも「可愛い!」でしたね。
ボキャブラリーの貧困だと思います。
2、言葉は変化しているとはいうが、全部ヤバイと大丈夫で表現できる(本当は出来てないが)つもりになったら、その日本語話者の、言語で伝える能力は衰えてると思うんだが。同じ語彙で様々な意味を表現するということは、何も言わないのと同じでしょ?まるで言語が出来る前の原始的なコミュニケーションのようだ。
3、まあ、 結構です も微妙な表現だよな。意味合い的には、肯定にも否定にも取れるから、普通は前後の意味合いから判断するけど、その曖昧さから詐欺電話とかだと揚げ足取りされてしまう。売り込み電話には、結構ですとは言わずに、要らないってはっきりいうようにしている。ってか、即切りのほうがほとんどだけど。
4、私も以前はコンビニでの店員さんとのやり取りで"大丈夫です"を使っておりましたが、最近は店員さんが外国人だったりすると大丈夫を使っても意思疎通が取れないという事に気付いたので今は店員さんの国籍に関係なく必要ない場合は"要らないです〜"という事にしております。やはり"大丈夫"の様に、どちらとも取れる表現は買い物での会計時のような一瞬で終わるものに対して使ってしまうと思わぬ方向へ行ってしまう事も有るので使わない方が良いなと思いました。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/5af170ba400d4640be5af69803d7ad6fd30c3c2e,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















