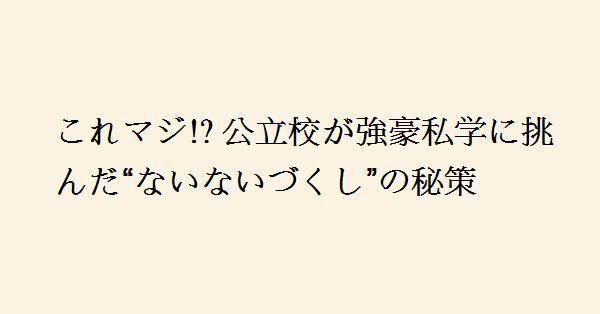
300字以内の事件概要:夏の甲子園で公立高校の活躍が注目されているが、今年の大会では過去最少となる6校しか出場していない。この背景には少子化による二極化があり、進学実績の高い私学がスポーツでも優れた実績を維持している。この中で、群馬県の県立高崎高校が21年ぶりにベスト4に進出し、その活動が話題となった。同校は偏差値70以上の進学校で、選手の確保に苦労しているが、練習メニューを生徒自らが考案するなど自主性を重んじた取り組みが特徴である。
ただし、準決勝では前橋育英にコールド負けし、現実の厳しさを痛感した。

コメント:公立高校が甲子園で苦戦する現状は憂慮すべき問題だ。少子化に伴うスポーツ選手の極端な二極化は、特に公立校にとって、推薦入試制度の欠陥を浮き彫りにする。この制度は公立校のスポーツ素材を一掃し、多様性を奪い去っている。さらに、私学中心の競技環境は、資金の不均衡が試合での明確な壁を生む。まず、地域コミュニティの支援により、部活支援の予算が増加することを考慮するべきだ。次に、地域間のスポーツ交流を促進し、エリート選手の流出を防ぐ仕組みを整備する。最後に、公立校の推薦入試制度の改革を通じて、強者のみに需給が集中する現状を打破することが必要である。私学が利する現行の仕組みに対し、積極的な対策で公立校に正当な競争機会を提供することが、長期的なスポーツ振興の鍵であり、社会的公正を成すものだろう。
ネットからのコメント
1、友達の出身地の甲子園出場校は、毎年全国から野球がうまい子が集まる私立だった。でも数年ぶりに、ほぼ地元出身者で構成された公立校が出場することになり、盛り上がりが半端なかったそうです。県外から来ている私立の子も親元を離れてさみしい思いをしているかもしれないけど、野球に没頭するための整った環境がある。限られた設備・時間・人員等の環境の中で、それでも甲子園に出場している公立校の方を応援したくなるのは、どうしてもしょうがないかなと思います。
2、私学強豪は、専用球場、室内練習場、内野ほどの広さのサブグラウンド・・・に代表されるように環境に恵まれている。使えるお金の違いもあるだろう。お金が多く使えれば、使えるボールも多いだろうし、バットもいいものをそろえられる・・・道具類においても差が大きい。さらに、広陵のように100人から150人ほどの部員がいる学校もある。おそらく声をかけてる子は中学時代の有望株なのだろう。有望株を一つの学校で「ごそっ」と獲得していれば、他の学校にいく有望株は減る。
いうなれば、他校の弱体化を招いてるともいえる。公立には厳しい状況になってるよね。高校生も、試合に出て、野球を楽しめる環境を選んだ方がいいのだけどね。そのほうが野球界にとっても未来が明るい。試合に出て、試合を重ねて、うまくなるのだろうからね。名のとおった学校に行っても、試合に出れなければうまくならないし、つまらんのだけどね。
3、私学の強豪は、授業は午前まで、午後は部活をずーっとやっている。公立はそういうわけにはいかない。それに、私学は全国から強力な選手を寄せ集めまくれるが、公立は寮がある学校はごく稀で地元の子のための学校である。こう考えると、学校は学業をするところのはずなのに、部活中心になっている学校があることに違和感。中卒の集まるための野球チームでも立ち上げれば?と思う。
4、兎に角甲子園に出場して名を上げて生徒を増やしたいこれが私立の手っ取り早く学校レベルの上げ方例えば岐阜県の大垣日大はその昔、公立落ちた子や公立受験できない子達の行く学校というイメージで実際地元では「ポン校」と呼ばれていたその為日大からプレッシャーがかかり急遽東邦で名をはせた阪口監督を招き入れ3年以内に甲子園出場を課せられたそして2年後、見事春の選抜に出場ししかも初出場で準優勝し大垣日大旋風(阪口旋風)を巻き起こし一躍有名校となりましたそれ以来着実に大垣日大野球は強くなり県内トップレベルを維持しそれと同時に大垣日大は生徒のレベルも上がりました今ではお年寄り以外の人は「ポン校」と呼ぶことはなくなりました
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/25407cb99f04fbf56d5a19be7a177da9000733f7,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















