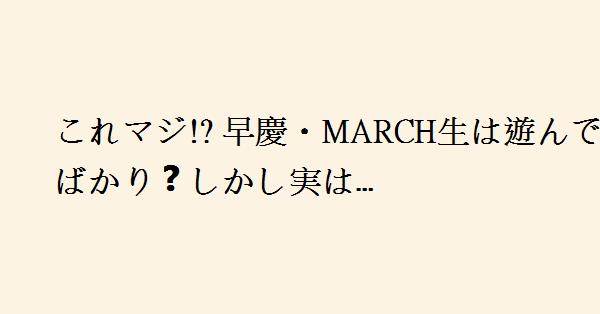
この記事では、学歴に関する評価の不公平さとそれに対する意見について、びーやま氏が自身の見解を示しています。特に、早慶やMARCHの学生が「遊んでばかり」という偏見がある一方で、頑張ることが評価に繋がる大切さを説いています。彼は学歴が一つの評価基準として優れている理由を説明しつつ、努力は必ず報われるとしています。さらに、びーやま氏は、努力の成果を客観的な証明として表現することの重要性を強調しています。
それにより、学歴の有無にかかわらず評価される道があるとしています。

今回の内容については、実際に高学歴としての評価が持つ意味に対する深い洞察を示しつつ、どのように他の形でそれを補完できるのかを言及しています。学歴のみで人を見る社会の風潮には強い異議を唱えつつ、それを超えて自らを表現していく方法について具体的なアドバイスを提供している点が重要です。特に、客観的な指標として学歴以外にも資格や成績という評価の基準を持つことの重要性を示しています。また、啓発的な視点で、努力が正当な評価に繋がる社会の実現を願う声として受け取れます。
ネットからのコメント
1、タイトルは実際の質問であるかのように装ったもので、中身は毎回同内容のものすごく浅い記事。これを初めて見たフリをして、なおかつ真に受けたコメントが多ければ多いほど、筆者はほくそ笑む。
なお、筆者の塾では、その関係者が自分の塾に都合の良い口コミを投稿していた(口コミ操作)という事例もある。 それはさておき、煽り強めの釣りタイトルとのバランスを考えてか、いつものように綺麗事もある。ただ、「どこの大学でも努力していれば社会で評価されるので安心してください」といった文言があるが、そもそも、筆者は社会全体を見渡すような視点で語れるほどの社会人経験があるとは言い難い。
2、早稲田の理工卒ですけど一般よりむしろ学院からの内部進学者の方が優秀でしたよ(全員ではありません、また単位習得の要領の良さや情報量の違いもあるとは思いますけどね)私は九州の公立出身ですが、高校入試で学院に受かるレベルではありませんでした。学科の3割が学院生、実業は学科に一人という時代ですので今とは違うと思いますけどなので内部進学生が一般に劣るとか記事を見ると「実際は違うのになあ」といつも思っていました。行ったいた学科が当時それなりに人気があったので、ある程度内進時に選抜されていたのかもしれませんけど普通に東大受かったやろうと思えるくらい優秀なのもの結構いましたよ
3、外資系企業でシニアマネジメントをしています。客観的に評価しやすいかどうかは現実的に重要だと思います。採用する立場では、学歴よりは、組織から求められている高いパフォーマンスを出せる人を必要としています。大学では業務経験はないので、大量の候補者から選考するときに、地頭の良い人が多そうな高い高学歴の人から採用されやすくなります。学歴とは別に語学力・資格など客観的に評価できるものがあれば有利です。入社後は学歴は関係ないですが、評価の段階で客観的な成果・アウトプットが重要になります。
4、正直、頭の回転が早く、いろんな知識があり、多様な客とネタをすぐ作れる。この程度は大学偏差値と概ね比例します。その蓄積がその学校への信頼となり、後輩たちも信頼される。そういうシステムです。Fランとは、一般入試で実質倍率がゼロの学校のこと、つまりは学力チェック無しで大学にはいれることを意味します。つまりは、高校入学程度の知識しか、担保されていないということ。だから、差をつけられるのです。嫌ならば、資格取りまくるとか経験積みまくるとか努力を。
というか、そういう努力ができる人は、その時点である程度のランクの大学に入学できています。自分から望んでFランクに入学する時点で、覚悟していなかったことを悔いてください
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/3ec1cc239f109d65342e03e8cb1432d3216d33c2,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















