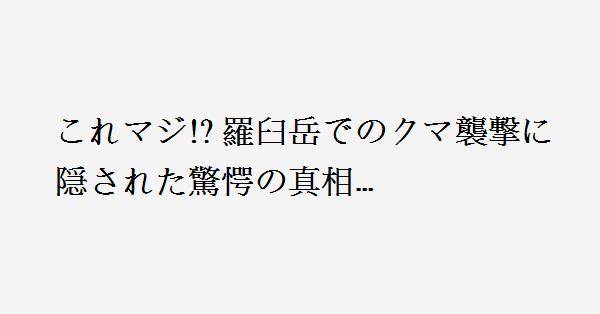
北海道の羅臼岳で2025年8月14日、登山中の男性(26)がクマに襲われ死亡しました。調査によると、襲撃したクマは事故前の8月10日、他の登山客に接近した母グマと子グマ2頭と同一である可能性が高いです。この親子グマは知床公園内の岩尾別地区で繰り返し目撃され、6年間にわたり人馴れした行動を見せていましたが、効果的な対策が取られず今回の悲劇を招きました。
事故発生時、男性はクマ鈴を持っていましたが効果的なクマスプレーは持っておらず、友人のスプレーもヒグマには有効でなかったため、防御の手段が不足していました。事故翌日、捜索隊がクマによって引きずられる男性を発見し、関与したクマが駆除されました。この事件を受け、知床財団は今後の安全対策と登山の在り方を再検討するとしています。

これは人と野生動物の共存を考える上で、大きな問題を突きつける事件です。今回の事故では、人馴れしたクマが長期間監視されながらも効果的な対策が不十分だったことが明らかになりました。知床国立公園のような自然と人が交わる地域では、クマによる事故を防ぐための監視と対策が不可欠です。まず、個体識別技術を駆使して危険個体を特定し、継続的な監視を行うことが重要です。そして、クマの活動地域について登山者への情報提供をさらに強化し、警戒エリアを事前に通達することが必要です。
さらに、クマ回避スプレーや警鐘グッズを備えることを登山の必須条件とし、より効果的な製品の指定や普及活動を推進すべきです。このような具体策を講じることで、自然と人が共生する地域において悲劇が繰り返されるのを防ぐことができるでしょう。



ネットからのコメント
1、そもそもが、登山道は本来境界の無い山に人間の都合で通路をつくり、区画する行為。野生動物がその区画に従うはずがなく、登山道を日々横切る不特定多数の個体がいることを想定しなくてはならない。ヒグマが生息する山に登るには、命の危険があることをまず十分に理解することが必要だ。そして、生息する野生動物や植物の性質を謙虚に学び、万全の準備を整えて行動する必要があるのだろう。
2、元々知床はヒグマの生息地というか縄張りだった地域です。正確な情報は解りませんが、ある報道によれば被害者はトレイルランをしていた?との情報があるが、2人で行ったのにどうして200mも離れていたのか、トレイルランなら理解できる。熊の生息地で走っているのを母ヒグマが見たら、襲うのも理解できる。ちなみに当方も以前に知床五湖まで行った事があるが、そこから先はヒグマの生息地と聞いてゾッとした事を思い出しました。今回の事件で知床の散策に対する安全を見直すべきなのでないかと思う。
3、熊に効果がないスプレーって、、なにを持っていたのかな?まさか殺虫剤レベルの代物か?いずれにしても危険個体が目撃され注意喚起されている場所への入山にしては装備も行動もヒグマへの警戒心がなく無知すぎると思った。
御冥福を捧げるが他の登山者を巻き込む恐れがある危険な行動(走る)だったと思う
4、詳細が判明し、走り山を下っていた男性を責める声もあるが、今回は不運による要因が大きいと思う。もしもタイミングが少しずれていたら、熊スプレーがせめて発射できていたら、羅臼岳は今後も20年熊被害のない山と言われていただろう。男性も熊親子もただ、悲運だった。トレランをされる方、登山をされる方は重々に気をつけて頂き、趣味を楽しんで欲しいと願うばかりである。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/a4ea99159d96872b3aab758e59d90efc26ba4c63,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















