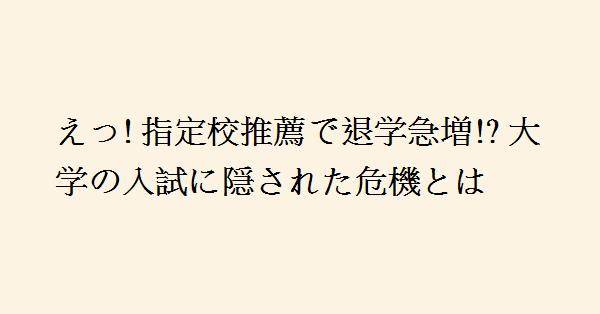
【事件概要】
2025年6月20日、共立女子大学で「なぜ、年内学力入試なのか」というシンポジウムが開催され、神奈川大学を含む複数の大学の入試担当者が登壇した。神奈川大学は、指定校推薦やAO入試で入学した学生の退学者が急増している問題を受け、国語・数学・英語の学力試験を課す「年内学力入試」を導入すると発表。2024年度の指定校推薦入学者の退学率は、2020年度比で145%と大幅に増加し、一般選抜者(110%増)を大きく上回っている。
この傾向は他大学にも広がっており、制度の見直しが急務とされている。

【コメント】
指定校推薦で入学した学生の退学急増という事態は、日本の大学入試制度に内在する重大な構造的欠陥を浮き彫りにしている。本来、校内選抜された“優等生”が、なぜ大学を辞めるのか――。それは、学力以外の曖昧な評価基準で入学が決まり、本人の適性や大学の学問的要求と著しく乖離しているからだ。制度の拡大を「多面的選抜」と美化し、裏で“早期囲い込み”を進める大学経営の姿勢も見過ごせない。
この問題の本質は、選抜の責任を高校に丸投げする大学と、形式的な推薦枠を増やすことで競争を回避する高校側の癒着構造にある。また、推薦者の進学後の追跡や、ミスマッチの検証も極めて不十分だ。
解決策は明確だ。①指定校推薦にも一定水準の学力試験を課す、②大学・高校間の推薦結果と進学後の実態を継続的に公開・共有する、③推薦制度の透明性と責任体制を明文化し、第三者によるチェックを導入する。
「信頼」で成立する制度が、今や「責任逃れ」の温床と化している。教育とは、本来、可能性を見極める厳しさの上にこそ育まれるものだ。今、問われているのは“やさしさ”ではなく、“誠実さ”だ。
ネットからのコメント
1、指定校推薦は高校での評定平均が基準になります。地方の公立の進学校だと評定平均が操作されることは無いですが、私立高校だと成績は高校によりけりで、公立高校なら評定がCレベルの生徒がAになっていることがよくあります。たとえば特進クラスの生徒は難関国立大学を目指させるので指定校推薦は受けさせませんが、運動部の一般クラスの生徒の成績に下駄を履かせて、指定校推薦を受けられるようにします。指定校推薦で進学できることが運動で優秀な生徒を集める手段になっています。
2、指定校推薦には優等生が選ばれるなんていうのは、ごく一部の偏差値の高い有名大学だけで、かなりの指定校推薦が余っているのが実情です。勿体ないから、高校側が生徒に指定校推薦を勧めることもザラにあるんじゃないですか?私の知人がそうでした。そもそも評定は、高校のレベル、同一校でも普通科よりスポーツ科や総合〇〇科等の方が遥かに高く不公平極まりない実態があります。
それを知っていて、進学する高校・科を選ぶ親子もいます。大学側も、経営のために学生を確保しているだけ。
3、指定校推薦の子の退学急増って、おばかな高校から指定校推薦でとるからだよ。大学に入ってからお勉強ついていけないんでしょ。一定レベル以上の高校からとればいいのに。都内の市部にある私立高校はさ、特進クラスと普通クラスあって、指定校推薦は特進の子たち貰えない。自力でいい大学に合格しろって。で、普通クラスの子たちが指定校推薦もらえる。その学校、中学の偏差値43とかだよ。そこから上がってきた子たちが指定校推薦もらっちゃう。そんなのが大学入学したら周りについていけないよ。
4、指定校推薦ではありませんが、某MARCH大学に宗教推薦で入学した知り合いの子は、通信制高校の評定を使ったそうです。普通の公立高校に入学出来なかった子です。真面目は真面目なのですが。退学はせず卒業は出来たのですが、一般企業には入社できず、病院の事務のパートをしています。推薦に使う評定には一定の基準が必要なのではないかと思います
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/ecba5a1153d76ed3018929bbb801f709341c55df,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















