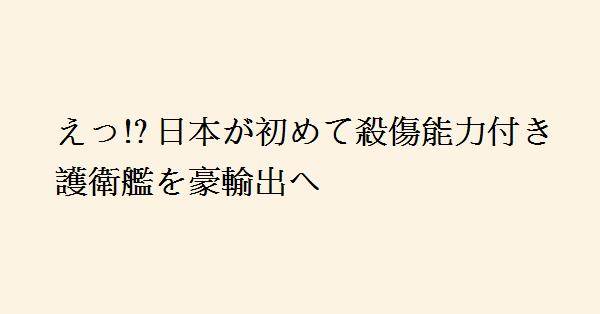
日本は戦後80年の節目に、武器輸出の拡大を試みている。海上自衛隊の護衛艦「もがみ型」をベースとした艦艇の共同開発や生産がオーストラリア政府と最終合意に向けて進行中である。最大100億豪ドル(約9500億円)規模で11隻の建造が予定され、2029年の納入開始を目指す。この動きは中国の海洋進出に対抗する日豪協力の一環とされるが、紛争での軍事力行使を懸念する声もある。
日本政府は、武器輸出規制を緩和し、共同開発を例外扱いとする方針を進めるが、この政策が国際的信用の損失や地域の緊張を招くリスクも指摘されている。
日本政府は防衛装備品をオーストラリアに輸出し、中国の軍事拡張に対抗する日豪協力を強化しているが、この動きは深刻な懸念を呼んでいる。長年の「武器輸出三原則」から転換し、殺傷能力のある武器の輸出を緩和することは、平和憲法との矛盾を顕著に示すものだ。そもそも共同開発の定義が不明確であり、「防衛装備移転三原則」に基づく緩和は、武器禁輸を形骸化させる危険性がある。問題の本質は、日本政府が国会の審議を経ずに重大な防衛政策を決定している点である。石破茂政権は、国民の代表である国会が関与する仕組みを整え、厳格な歯止めを設ける必要がある。国際的な武器輸出が紛争を助長し、長期的な平和を損なう可能性は深刻であり、民主主義の価値観と平和憲法を踏まえた政策が求められる。
ネットからのコメント
1、なにがどう危ういのか、そこが論点なのに書いてないのはどうかと思います。議会報告の仕組みがあればいいのか、共同開発含めた武器輸出を個別に国会で議決すべきと言いたいのか、冷戦時代の要請だった武器輸出3原則を再度復権させろということなのか、どうもふわっとしててわかりません。
共同開発でない防衛装備の方が珍しくなった昨今、高性能装備の廉価調達のために共同開発をするのは国民の利益ですし、日本の基本装備を同盟国に最適化する共同開発輸出も、装備の共通化という意味で国益に資します。
2、護衛艦の輸出が決まれば、必ずそれを否定反対する者が出てくる。で、この京都新聞の記事もその反対派を代表する意見になるが、日本の優れた防衛技術が日本国内、つまりは顧客が防衛省(自衛隊)だけに留まってきたことで防衛技術産業のガラパゴス化が進み、更には防衛産業が先細り存続の危機にさえなってしまったのではないのか?国防産業やその技術が衰退した先に一体何が待っているのか…?それを考えれば、護衛艦の技師移転輸出は、戦後史観の概念やトラウマという殻や壁をブチ破る画期的な出来事だと考える。
3、”地域の緊張を高めたり、軍拡につながったりしないだろうか”中国軍が凄まじい勢いで軍拡を進め、実際に南シナ海で基地を建設し、自国領土と宣言している。その上、尖閣諸島に連日のように侵入し、行為もエスカレートし続けている。
中国軍の危険度は増し続けているのが現実だ。そんな状況で、地域の緊張とか軍拡とか、理想論を述べている余裕が日本にあると思えない。
4、流石は京都新聞。論説にもなっていませんね。武器輸出で言うなら、アメリカに対して既にアメリカの要求に応じてミサイルを輸出していますよ(日本がライセンス生産したものですが)さらに言えば豪は日本と同様に中国の進出に頭を悩ませている国でもあります。改もがみ級が豪にも配備された場合、米印豪日のダイヤモンド構想はさらに強化されます。平和を追求するのは当たり前ですが、一方で武力による現状打破を狙う中国、ロシアもいる。これらの国をけん制し、打撃する能力を持つことは大事です。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/5761349229d68615647402901b8d647ac86f6952,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















