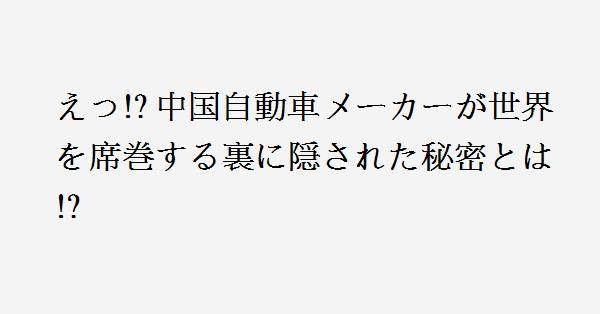
事件概要:2023年において、中国の自動車産業の急成長が世界経済に大きな影響を与えている。米中間の関税措置の停止期間延長の一方で、中国は自動車販売台数で世界1位に躍進し、その数は3143万台と米国の1634万台を遥かに上回る。これにより、日本自動車産業は両国への輸出に依存している現状で大きな影響を受ける可能性がある。中国の自動車メーカーは、特にEV分野で技術開発を進め、世界市場での競争力を高めているが、輸出先は主にメキシコやロシアなどに限られ、米国や欧州にはまだ進出していない。
このような動きは、日本にとって大きな脅威となっている。

コメント:中国の自動車産業が急速に台頭している現状は、日本の自動車産業にとって大きな脅威だ。一度は世界をリードした日本も、今では米中の競争に後れを取っている状況がある。まず、企業間で革新的な技術開発を促進し、EV分野での競争力を取り戻す必要がある。次に、日本政府が自動運転技術への投資を強化し、国際的な協力を通じて市場を拡大することが重要だ。また、より柔軟な労働制度を導入し、迅速な開発体制を整えることで、中国のような24時間稼働の効率性を合わせ持つべきだ。これこそが、日本の自動車産業が再び世界に飛躍するための鍵となる。自動車産業の未来は、日本の積極的な改革と市場適応力の進化にかかっているのだ。
ネットからのコメント
1、そもそも自動運転をドライバーが望んでいるのかという話。
政府が高額の補助金出してもEV車が普及しないのは、別にドライバーはそれを欲しいと思わないから。充電スポットも増えないのは普及しないとわかってるから。もし完全自動運転が実現すれば、別にマイカーなんてなくてもレンタカーで十分。勝手に家まで来てくれて目的を果たせば勝手に店まで帰ってくれる。運転することを楽しみたい人は車に乗る機会も減るだろうし、販売台数も落ち込むかもしれない。
2、「補助」程度なら兎も角、依存寄りの自動運転であれば自動車側だけではなく交通インフラ側の整備も必要のはずで、それが成されずに稚拙に普及をさせているからこそ、世界各国で自動運転に関する事故が起きているのでは。開発は兎も角、市場への普及についてはそこまで注力すべき段階ではないように思うのだけれど。
3、そもそも日本の人口も労働人口も少ないのだから、販売台数で優劣を決める方がおかしいというものです。アメリカ市場でのトヨタやホンダの信頼性が大きく揺らいだ事実はありません。一方中国EV電池の発火リスク問題に振り回されてはいけません。その為にEV車販売数で後れを取ってる事は決して後退では無いのです。
むしろHVを維持してきた事が長い視野で懸命な判断でした。EV開発はHVを総合力で凌げましたか?まだそんな事はありません。ましてや自動運転って、日本では専用線路上の自動運転は既に実現していますが、一般道では仮に技術があっても「刑事責任の問題から」絶対に実現すべきではないのです。車の誤作動や歩行者の飛出しを避けられなかった事で人身事故を起こした場合、誰が刑事責任や賠償責任を負うんですか?
4、政府による補助金と法規制緩和や特例があってこその急激な拡大。日本において電動キックボード展開や訪日中国人向け免許取得緩和などが政府の政策として行われたように、中国共産党政府によるEV補助金政策や、欧州や新興国の一部でも事実上の中国車向けEV補助金政策が行われてきたし、自動運転タクシー・バス普及においても法規制緩和と過程のいくつかの人身事故の軽視や不問も政府が容認している。日本でもそのように多額の税金を投入したり、法を多少捻じ曲げたり人命軽視すればEVや自動運転はすぐに普及できるが、国民はそれを望まないということ。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/94a85c8741930862a4d1cae13a7c295f077a16ac,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















