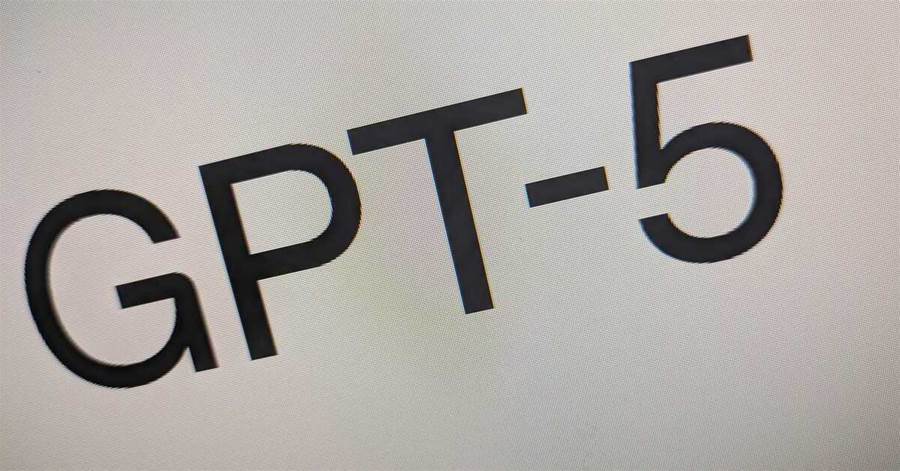
米OpenAIは8月7日、次世代AIモデル「GPT-5」を発表し、同日より無料ユーザーを含む全ChatGPT利用者に提供開始した。従来の「GPT-4o」「o3」「o4-mini」「GPT-4.1」「GPT-4.5」は置き換えられる。GPT-5はコーディング、数学、ライティング、医療、視覚認識などで新たな最高水準を達成し、特にコーディング機能が強化された。
無料利用には回数上限があり、超過時は「GPT-5 mini」に切替。有料会員は利用回数が増加し、Pro会員は無制限利用と最高性能の「GPT-5 Pro」が使用可能。

AIの進化は目覚ましいが、その影に潜む課題は見逃せない。性能向上や利便性の向上は歓迎すべきだが、全モデルの一斉置き換えはユーザーの選択権を奪い、既存環境との互換性問題や業務上の混乱を招く恐れがある。背景には、市場シェアの独占や利用データの囲い込み戦略が透けて見える。解決のためには、①旧モデルの並行提供による移行期間の確保、②APIや機能の後方互換性保証、③透明性の高い変更理由と影響範囲の説明が不可欠だ。技術の進歩は本来、人々の自由を広げるためにある。もしそれが便利さの名の下で選択肢を狭めるなら、それは進歩ではなく支配への一歩に過ぎない。
ネットからのコメント
1、AIの進化がここまで進むと、正直なところ、普通のホワイトカラーの仕事はどんどん減っていくと思います。事務作業や簡単な分析などはAIがあっという間にこなしてしまう時代。残れるのは、ごく一部のスキルの高い人たちだけになっていくのかもしれません。その一方で、どうしても人の手が必要な現場仕事やサービス業のような肉体労働は、むしろ今後も重要になっていくはずです。結局、AIが進めば進むほど、社会全体は「二極化」に向かっている気がします。
2、AIが利用されることで、膨大な学習データがユーザーにより提供され続ける。さらに賢くなるAIとどう付き合うか。ほかの方のコメントの通り、何もかもすぐにAIに頼り考える力を自ら放棄するのではなく、AIの力を借りて業務の一旦を担ってもらったり、自分に足りない知識を補ってもらったりといった賢い付き合いが求められてきますね。AIも万能ではなく間違いも起こします。貰った回答を疑って自分で照合するとうまく知識を吸収できる印象です。
3、仕事上パソコンは使えても、Google検索で頑張ってイチから作る人と、複数AIを使いこなしてる人とで、アウトプット時間や品質の差が物凄いことになってる。
誰でも使えるGPT5登場により、これを前提とした生き方が試され、AI格差も大きくなるのかもしれない。まあ、WindowsやMac OS、果てはスマートフォンにもOSベンダー標準AIのインタフェースが装備されており、知らないうちにAIを使ってる人もいる訳で、なるべくなら、AI格差が大きくならず、この様に『知らないうちに使えてる』世界になって行って欲しい。
4、さっそく、O3+DeepResearchにお願いしてた課題5をGPT5で分析させました(ソフトウェアのバグ探索、設計方針、新規アイディアなど)O3+DRでは明確なハルシネーションを起こしていた部分(つまりおそらく学習されてないところ)では適切とおもわれる対応、つまり取り扱わないまたは不明であるとしています。課題解決にいたる結論を出しているかというと2つはO3よりも期待したものですが、3つはあまり変わらない印象です。主にプログラミング向けには改善されていると評価をみかけるため、エンジニアたちの評価はこれからになると思いますが、一定の進化をしたようですね。
モデル選択がシンプルになったことは歓迎されるとおもいます。他社の動向もきになります。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/57d318f18f44087558794d26b393f91ce60ea90a,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















