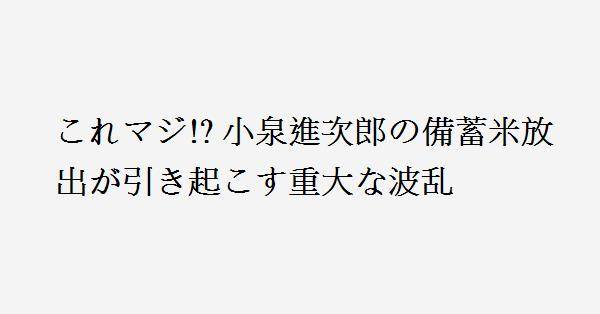
事件概要:日本政府は2025年2月から米の価格高騰に対応するため、約81万トンの備蓄米を放出し、そのうち61万トンが既に市場に出されました。この措置により、米の供給が増加し、価格が安定したとされています。特に、小泉進次郎農水大臣が就任後、迅速な放出が行われ、消費者は5kg約2000円で購入できるようになりました。しかし、1993年の大凶作を契機に始まった備蓄米制度を利用した価格調整が、農家への影響を懸念させ、政府の対応には疑問も呈されています。
備蓄米は本来、米の供給が不足した際の安全網として運用されてきましたが、今後は需給バランスの調整方法を見直す必要があるとされています。

コメント:備蓄米の放出による即効的な価格安定は、消費者にとってはありがたい反面、農家に与える影響は無視できません。政府が本来の目的を超えて価格調整に備蓄米を使用することにはリスクが伴います。特に、農家の経営圧迫を招く恐れがあり、長期的な視点で見た場合、農業の持続可能性を危うくする可能性もあります。
今後、米の供給と価格を安定させるためには、備蓄米の放出に頼るだけではなく、長期的な需給調整政策を講じることが求められます。例えば、作付面積の拡大や効率的な生産体制の構築、消費動向に基づく柔軟な生産調整が必要です。政府が政治的な意図から価格調整を進めることは避け、米の自給率向上に向けた真摯な取り組みが欠かせません。
また、再備蓄の問題を深刻に捉え、災害時に備えた備蓄米の安定運用を確立することが不可欠です。
ネットからのコメント
1、高温・不雨等で今年の新米は収穫量が減り、値段が上がりそうだ。素人として感じる。備蓄米を8月末までに売りつくせとしたが、間に合いそうにもない。だが、それが幸いするのかもしれない。備蓄米の販売期間を延ばせば、新米の収穫減量分をある程度補えるだろう。国民それぞれの生活に合わせて新米か備蓄米を選択するようにすればいい。
2、今まで米が異常に安かったのはその通りと思う人が多いと思いますよ。2022年辺りから様々な物が値上がりしていましたから米も当然上がっても仕方ない。ただ上がる速度と幅か異常だったし、米はなんと言っても主食ですから混乱が大きかったのでしょう。国民の大半は可処分所得が増えないままでの物価高騰を迎えて苦しいですから、なるべく生活費を抑えることをしないと生きていけないので高いな、と思えば主食と言えども工夫して消費量を減らすか、代わりの物を渋々でも選択するしかないので、結果米離れが進むと思う。
やはり米に関しては市場原理にまかせずある程度の公的な管理が必要ではないだろうか。
3、そもそも、歴代政権の失策をカバーする為に、備蓄米の放出という禁じ手を犯している時点で、褒められた放出ではありませんよね。消費者の反発を抑える為に、米の安定供給、べいかを下げることを目的として放出した反面、農家の経済活動を封じたともいえます。実際は、農家からお米を買った中間業者が恩恵を受けていたわけですけど。これから、秋以降米が不足したら、いよいよ輸入に頼るしかなくなる訳ですけど、どうやって乗り切るのか見ものですよね。
4、農家といっても水稲していない農家に言われてもな〜、というのが本音。うちは野菜(施設、露地)と水稲をしているけど、水稲は規模とコストが比例しやすい作物です。黒字になるにはある程度の規模は必要ですが、大きくしても肥料や薬剤を減らせるわけでもなく、農機も専用なのでコストがかかりやすいです。また、コメはトウモロコシやトマトのようにバイネームでより高く売れるわけではなく、ある程度で頭打ちになるのが現実なので、コメは規模を大きくすることが必ずしも正解とは言えないと思いますよ。
引用元:https://news.yahoo.co.jp/articles/c673e74f3ee33addfd831d9f979454e1d3c7710f,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]



















